交流
2023年09月27日
CCC チャレンジファンド2023公開コンペ
2023年度 地域・ボランティア活動 展示会・講演会・発表会

2023年6月25日(日)星が丘キャンパス 5号館1階アクティブ・ラーニングスタジオ
学生団体が大学からの支援を得るために今後の活動方針を発表。
地域の課題や今後の目標、活動に対する想いを先生方に伝えました。
本学の「コミュニティ・コラボレーションセンター(以下、CCC)」では、学生にボランティア団体を紹介し、自主性や実社会で役立つスキルを養う機会を提供しています。学生団体はそれぞれのコンセプトに従って社会貢献活動に努めていますが、なかには遠方に足を運んだり、イベントを開催したりすることで費用が発生することもあります。CCCでは、そのような学生たちをサポートするため、「チャレンジファンド」というコンペ形式の資金助成制度を設けています。助成を希望する学生団体が実績や今後の活動予定を発表し、採択されることで、愛知淑徳大学後援会から1年間の諸経費を援助してもらえます。
2023年6月25日(日)に実施された公開コンペでは、9団体がエントリー。各団体が地域社会の課題に対する取り組みや想いを伝えました。
以下では、各団体の発表内容をダイジェストで紹介します。






学生団体NAO/NAO工房


トップバッターを務めたのは、名古屋市西山地区で子どもの居場所づくりを目指している「学生団体NAO」。CCC主催の授業「キズナプロジェクトB」の履修生が立ち上げた、今年誕生したばかりの学生団体です。西山地区の居場所づくりモデル「暮らせる図書館」や西山商店街と連携し、ワークショップやイベントなどを開催しています。子どもが安心できる場所を作り上げるだけではなく、子どもの保護者や地域の高齢者など多様な世代との関わりを生み出すことも目的としています。先生から「活動において大学生であることは活かせているか」という質問が寄せられた際には、「学部での学びを発揮しながら、大人と子どもの中間の視点でさまざまな人とコミュニケ―ションを取れていると思います」と堂々と答えました。
らぶ♡やお/子どもの居場所づくり


子ども食堂の活動を通じて、子どもの居場所づくりに取り組んでいるのが、2023年4月に発足した「らぶ♡やお」です。月に1~2回、地域コミュニティが運営している子ども食堂や、NPO団体による食を必要とする子育て世代にむけた弁当配布のお手伝いしています。また、子どもたちとの会話や、遊び、勉強を通して交流を深めています。現在の目標は、長期的に活動をおこない子どもをはじめとした地域住民との関係を作り、子どもたちが安心できる場を生み出すこと。子どもたちの声に耳を聞きながら、よりよい活動を目指したいと語りました。
Fsus4/音楽というコミュニケーションで1つになろう


「Fsus4(サスフォー)」は、高齢者施設や障がい者施設に訪問し、音楽演奏を通じて施設利用者との交流を図る学生団体です。2022年までは新型コロナウイルスの影響で訪問演奏の機会が限られていましたが、今年度は積極的に施設に足を運び、直接音楽を届けたいと活動に取り組んでいます。施設利用者と学生が、同じ空間で音楽を楽しむことを目標とし、音楽を聴いた人にとって少しでもエネルギーになったり、笑顔に繋がれば嬉しいという熱意を語りました。今年で11年目になるFsus4ですが、教員からも10年も続けられた理由を尋ねられると、「利用者と学生との交流を途絶えさせないことが重要だと思うからです」と、先輩たちから受け継いできた活動への想いを込めて返答しました。
チームわんわん/Plusワン~介助犬の輪を明日に繋ごう~


「チームわんわん」は、介助犬や介助犬を必要としている人々の現状を、より多くの人に知ってもらうために活動しています。社会での介助犬の認知度は低く、介助犬の頭数が少ないことや、飲食店で同伴拒否が発生している課題があります。またこれまでの活動で、介助犬の認知度が地域を問わず異なるという気づきがありました。今年度は長久手市外でのイベントにも参加し、また長久手市内の小学校での特別授業をおこないます。参加者とのコミュニケーションを図りながら、「使用者さんと介助犬がより生きやすい社会」を実現することを目的に取り組んでいきたいと語りました。
エコのつぼみ/守ろう伝えよう!里山保全!


全国で問題となっている放置竹林問題や竹害の解決・改善に取り組んでいるのが「エコのつぼみ」です。放置竹林による里山の生態系の崩れや、竹林整備の担い手の不足や後継者不足といった課題に対して、まずはNPO法人モリビトの会の方とともに竹林整備をしたり、 子ども向けワークショップを実施したりするということをしています。これらの活動を通じて、「環境問題について興味のある人もない人も小さなことからやさしい行動をとってもらえたら嬉しい」という目標を伝えました。また先生からは「竹害は竹ではなく人間の問題であることもワークショップで伝えてほしい」という活動へのアドバイスをもらいました。
ユニこまPlus+/当たり前から新たな気づきへ


「ユニこまPlus+」は誰もが来たい服が着れるという環境の実現に向けて活動をおこなっています。既成のファッションを障がい者も着られるように、服のリメイク活動に取り組んだり、障がいの有無関係なく誰もが簡単に取り組めるスポーツである「ボッチャ」を通じた交流も積極的に進めています。施設に通う中で当事者から「試着室に入れず諦めたことがある」「介助者のために無意識に諦めている服がある」という声を聞いており、改めてリメイク活動の必要性を感じたことを伝えました。そして、障がい者というマイノリティの中にさらなるマイノリティを作らないためにも活動していきたいという熱い目標を掲げました。
アミーゴ/子ども応援団


愛知県には、外国にルーツのある日本語指導が必要な児童が58,000人おり、「授業についていけない」「クラスメイトとのコミュニケーションが難しい」などが課題になっています。そのような子どもたちを対象に活動しているのが「アミーゴ」です。学生が子どもと一緒に本を読む「多読活動」や、子どもたちが少しでも自身の将来を想像できるように、子どもたちの夢や好きなことを共有する「ドリームマップ作り」、ドリームマップ作りのヒントを見つけるための「大学見学」などをおこなっています。発表を聞いた先生からは「子どもたちが大きくなったときに『あのとき日本語を教えてもらってよかった』と言ってもらえるように、長期的に活動をしてほしいです」とエールが送られてました。
そとそと/そとへと繋ぐ!豊田市とジビエのディープな世界


自然豊かな豊田市で、豊田市とジビエの魅力などを伝える活動をしている「そとそと」。すでに豊田市青少年センターの助成金制度に採択されているが、 豊田市外の地域での活動を増やしていきたいという意欲を語りました。今年度は鹿革を使ったワークショップブースの出店や観光パンフレットの作成に加え、ジビエ料理を楽しんでもらえる機会を増やしていくことを計画しているとのこと。またジビエの魅力を伝えるだけでなく、豊田市山間地域の過疎化や鳥獣被害のこと、有害鳥獣の9割廃棄なその課題についての学びも提供していきたいと語りました。
きらきら☆したら/伝えよう、きらきら輝くしたらの魅力
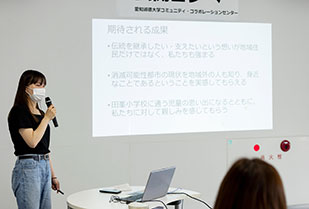

学生団体「きらきら☆したら」は、愛知県設楽町の住民の方々との交流の中で学生が感じた地域の魅力を、さまざまなイベントへの参加やSNSでの発信を通し、伝えています。活動拠点としている田峯地区は、小学校が今年度で廃校になり、田峯地区の住民によって演じられる「田峯歌舞伎」の継承が難しい状況になってきました。これまでは関係人口の増加や地域の行事を支える活動を行ってきましたが、今後は住民との関係性をより大切にしながら、伝統文化をできるだけ多くの人々の記憶に残すことを目的に活動を続けていくことを決心しました。先生からは「DVDの記録媒体にアーカイブを残し、後世に伝えていくのも良いのではないか」とアドバイスをもらいました。












