まだこの世にない「味」を生み出す
食品開発者になろう!
まだこの世にない「味」を生み出す
食品開発者になろう!

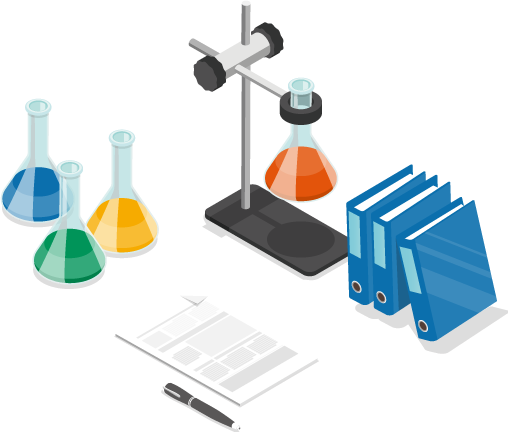
豊かな食生活を支え、健康を担っている食品関連産業は、
ライフスタイルの多様化や時代背景に大きく左右されることなく成長を続けています。
中でも新しい商品を生み出し、食品業界に革新を起こす「食品開発」の分野に必要なのは、
おいしさを科学的・技術的に探究する「分析力」です。
愛知淑徳大学の食創造科学科では、食に関する多様かつ専門的な知識と技術を磨き、
これからの食品関連産業を担う人材を育成します。

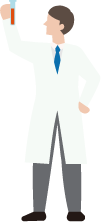
自分のアイデアを
形にできる!

新しい味を
探究できる!

多くの消費者に
手にしてもらえる!
食に関する知識が
豊富になる!
業務の幅が広く
新しい挑戦ができる!

アイデアやイメージを商品化していく「食品開発」は、安全性の確保や品質の維持など、乗り越えるべきハードルもたくさん。さまざまな制約の中で、いかにして新商品は生まれているのでしょうか?実際の「食品開発」の過程を見てみましょう。
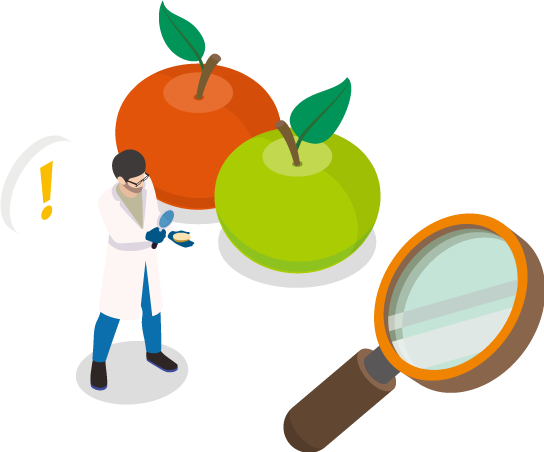
おいしさの3大要素といわれている「味」「香り」「食感」。この構成比が少し変わるだけでおいしさは大きく変化します。そのため、数値化したデータをもとに、原材料の配合や製造条件、形状などを検討し、理想の「おいしさ」を追求していく必要があります。私たちが食べて感じる「おいしさ」の正体は、緻密に計算して生み出されたものであり、食品開発に分析は欠かせないのです。愛知淑徳大学の食創造科学科は、「食品開発」を「食創造」として捉え、食に関わる分析力を養います。
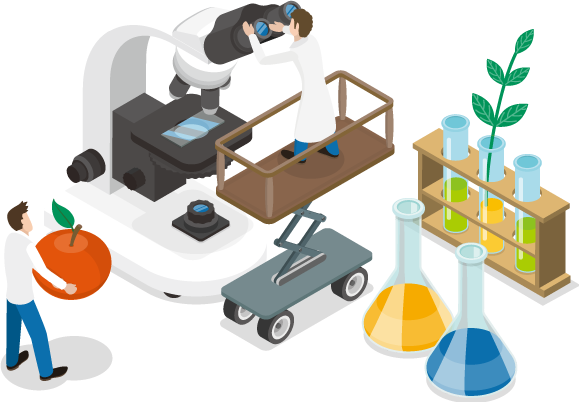
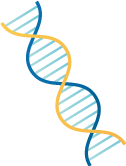
グミのおいしさの要因の一つに食感があります。クリープメーターを用いてグミを分析することにより、かたさ、粘着性、破断性、凝集性など食感を測定できます。見た目は似ているのに人気のグミは、糖衣がぱりっとし、中はもちっとした食感の変化があって、歯にくっつきにくいものでした。分析によって、おいしさの特徴を客観的に捉えることができます。
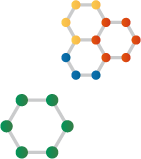
炊きあがりが美しく、良い香りがして、ねばりと適度なかたさがあるお米が「おいしいお米」といわれています。このうち、ねばりなど口の中に入れた時のテクスチャー(口ざわり)がおいしさのカギ。ねばりは炊くことによりお米の中のでん粉という成分が糊化(こか)することでおこります。この糊化をラピッドビスコアナライザーで計測することでご飯のおいしさを評価でき、最高粘度が高く、ブレークダウンが大きいほどおいしいお米といえます。

食創造科学科なら、
「食品開発」の要となる
分析力を養うための
授業や施設が充実!


実際に食品中には、どのような成分がどれくらい含まれており、どのような変化が起こるのか、身近に利用されている食品を題材として、定性実験や定量実験をおこなうことにより理解を深めます。
実験器具や試薬類の正しい取り扱い方といった基本的な操作から、さまざまな原理でおこなう精密機器分析の手順を身につけ、分析の目的や成分に応じて適切な分析法を選択できる力を養います。
食品中の細菌検査や、食品添加物の定量分析、鮮度検査、食品中の異物試験などをおこない、食材、製造から食卓までの食品安全に必要不可欠な分析手技を身につけます。
調理の過程における食材の状態変化を物理的・化学的な測定により捉えながら、物性の変化が食味や嗜好性にどのような影響を与えるか官能検査により評価する方法を習得します。
2023年完成の新1号棟の4・5階に食創造科学科の専用フロアを整備。
最新の設備が整った、実習室・実験室の他、専用ラウンジなども設置されています。

▲ 食品加工実習室

▲ 培養室

▲ 官能評価室

▲ 精密機器室
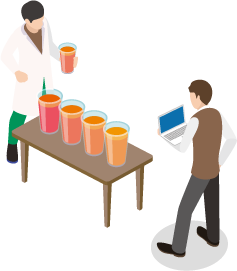
コミュニケーション力
プレゼンテーション力
好奇心と探究心
アイデアを形にする
提案力
ニーズをつかむ
分析力

食創造科学科で養える食に関する総合的な知識・技術を活かせるのは、食品業界だけに留まりません。「食」をコンテンツとして扱う業種は多種多様で、食に関する記事を取り上げる出版業界や食品関連企業に融資やコンサルティングを行う金融機関、食をキーワードに地域活性化を行う地方公務員など、活躍が期待される場は想像以上に広がっています。

アイデアを発想する力を活かし、最新の市場や消費者のニーズを捉えた新商品を企画し、実際に商品化を実現していきます。
消費者心理を読み解き市場創造を可能とするマーケティングの知識を活かし、マーケティング戦略を立案・実行します。
食品の流通の基本知識と消費者の立場からより良い食品選択を行うスキルを活かし、生産者と流通、販売をつなぐ役割を果たします。
食品衛生管理について学ぶことで品質管理の重要性を理解し、ジャンルを問わず高品質な製品を世に送り出すことに貢献します。
まちづくりや地域活性化などのテーマとして食が取り上げられる機会も多く、国や地方公共団体の職員として、政策立案や実行、行政サービスの改善に貢献します。
課題を解決していく視点や新しいものを生み出す発想力で、新規事業の立ち上げや起業家としての活躍も期待できます。
●製造業:加工食品、食品飲料など
●総合商社:食品原材料など
●専門商社:食品卸など
●外食:百貨店、食品スーパー、ドラッグストアなど
●行政:公務員
●フードコーディネーター
●食生活アドバイザー
●大学院進学など
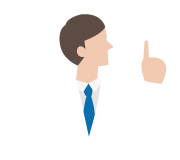
Q.
健康栄養学科と食創造科学科の違いは何ですか?
A.
健康栄養学科では、管理栄養士の国家試験受験資格取得のための授業が中心です。一方、食創造科学科は資格取得にとらわれず、食に関する幅広い分野を学ぶことができ、さらに自分の興味のある分野を深く探究することができます。

Q.
取得できる資格・免許はありますか?
A.
「食品衛生管理者任用資格※」
「食品衛生監視員任用資格※」
「司書」「学芸員」が取得できます。
※ 任用資格:採用後、特定の業務に任用される時に必要とされる資格

Copyright(c). Aichi Shukutoku University.
All rights reserved.