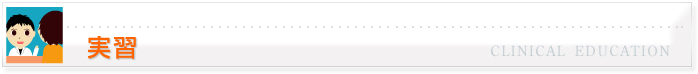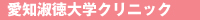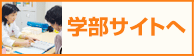言語聴覚士になるための「心と知識と技術」を実践的に学びます
本専攻では、実践的に言語聴覚士の仕事が学べるよう、学内外でさまざまな実習の機会を設けています。
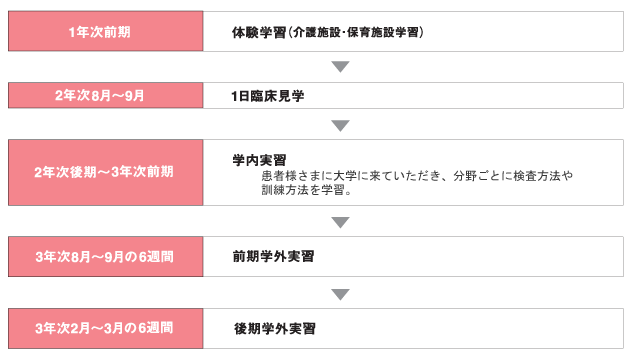
1日見学
2年生の夏季休暇中に、病院、老人保健施設、福祉施設、学校など、言語聴覚士の働く現場の1日見学をします。
学内実習
2年生後期から3年生前期まで1年間、小児領域(発達障がい、構音障がい)、成人領域(失語症、構音障がい、嚥下障がい)、聴覚領域について、当事者の方にご協力いただいて、学内の教員の指導のもと、臨床実践の学習をします。
実習の一部は愛知淑徳大学クリニックで実施しています。
“実際に、言語障がいをお持ちの方々と接するのは緊張するし、準備やレポート課題が大変。 でも、関わりの体験は、楽しくてやりがいがある。” と学生たちに好評です。

本専攻では、愛知淑徳大学クリニックの協力のもとで、より臨床現場に近づくための体験的学習を行っています。
言語聴覚士のスタッフの指導を受けながら、高度な臨床能力と豊かな人間性を培い、学外実習への心構えを育みます。
学外実習
3年次の夏季休暇、春季休暇を活用して、各々6週間、ベテランの言語聴覚士のもと、臨床実習を行います。
この学外実習は、4年間の大学生活で、心に残る体験の筆頭に挙げられます。
病院の臨床や教育現場の見学、評価、指導・訓練の体験をさせていただき、知識、技術を身につけるだけでなく、人間的にも大きく成長する機会となります。
また、全学年で行うその実習報告会も恒例の行事となっています。
これが、下級生にとっては実習に対する事前学習の良い機会となっています。
学生インタビュー
- 「心」に寄り添いながら訓練をおこなうことの大切さを実感しました。
-
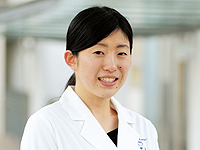
4年生 中島 珠美さん
一人ひとりの心に寄り添う言語聴覚士になりたい!
この思いが強くなったきっかけが、学外実習でした。
6週間、難聴幼児通園施設で、子どもたちと触れ合いながら構音訓練などの実践を重ねました。
実習中に心がけたのは、子ども目線で考えること。
学内実習で患者さまの個性を理解してコミュニケーションをとることが訓練の成果につながると実感していたため、子どもの好きなキャラクターのカードを手づくりして訓練に活用するなどの工夫をしました。
その訓練中に目にした子どもたちの輝く笑顔が、今も私の胸を熱くし、日々の授業やゼミでの難聴児に関する研究に励む原動力になっています。
ボランティア活動
本専攻は、4年間を通じて、地域でのボランティア活動を推奨しています。1、2年生は、本格的な実習が始まる前の準備にもなっています。
また4年生になってからは、卒論、国家試験勉強に取り組む傍ら、これまで行ってきたボランティア活動を継続し、現場との接点を持ち続けます。
ボランティア活動についてはこちら