追究
2024年07月18日
メディアプロデュース専攻 宮田ゼミ「演習Ⅰa」デザイン提案のための見学&ディスカッション

2024年5月11日(土) 日本貨物鉄道株式会社(JR貨物)東海支社
2024年5月14日(火)、5月21日(火) 長久手キャンパス712教室
JR貨物 東海支社の皆さまへ、
貨物列車をけん引する機関車のラッピングデザインを提案。
提案のための見学や勉強会をおこないました。
本学の創造表現学科 メディアプロデュース専攻では、デジタル化に伴って多様化が進むメディアの特性を理解し、社会に対し適切な情報発信ができる人材の育成をめざしています。中でも宮田ゼミでは「メディア社会とデザイン」をテーマに活動し、これまで学外の機関や団体、企業の方々にご協力いただきながら、依頼主が抱えるさまざまな課題をコミュニケーションデザインの力で解決に導こうとしています。
2024年度前期の3年ゼミでは、日本貨物鉄道株式会社(以下、JR貨物)東海支社の方々にご協力いただき、貨物列車のラッピングデザイン提案に取り組みます。
5月から7月にかけておこなわれるゼミでの取り組みについて前半は5月におこなわれた内容をダイジェストでレポートします。
2024年5月11日(土)第1回目
名古屋貨物ターミナル駅と
愛知機関区、稲沢機関区を見学しました。




2024年5月11日(土)、ゼミ生たちはJR貨物東海支社さまの名古屋貨物ターミナル駅を見学するために、あおなみ線の中島駅に集合。ここから徒歩で社屋まで移動し、東海支社の皆さまからPR動画などを交えながら会社の説明をしていただきました。続いて名古屋貨物ターミナル駅について森下駅長から説明していただいた後、屋上に移動。駅構内を俯瞰することで全体像を把握しました。また、名古屋貨物ターミナル駅の業務として、フロント(窓口)の業務内容をご紹介いただきました。ここでは女性社員が2名でコンテナの操配や列車が遅れた際の対応・調整などをおこなっていることを学びました。次に構内へ移動。構内ではフォークリフトに乗ってコンテナを移動させる社員やコンテナをITで管理していることなどを話していただき、実際にコンテナの中にも入らせていただくことができました。




昼食を取った後、午後から再びあおなみ線とJR在来線を乗り継ぎ、稲沢駅に移動。ここには愛知機関区と稲沢機関区があり、愛知機関区では車両のメンテナンスを見学、稲沢機関区では運転手の仕事について見学しました。


愛知機関区では副区長の濱口さまから説明をいただきました。ここでは約80名の社員が働いているといい、機関車と貨車を同時にメンテナンスしている珍しい機関区であることを教えていただきました。2班に分かれ、機関車のメンテナンス風景を見学。運転席にも入らせていただき、実際の運転現場の雰囲気を感じ取ることができました。


続いて稲沢機関区に移動。ここはJR貨物さまの中でも200名を超える運転士が所属する社内最大の機関区です。ここでは運転士が仮眠を取る場所や運転前に業務の確認をおこなう点呼場を見学。さらに運転シミュレーターも体験させていただきました。シミュレーターではさまざまな天候や時間帯を再現でき、線路内に動物が飛び出してきたり、土砂崩れが起こったりと突発的なアクシデントも設定することができます。学生たちは初めて操作する機関車に最初は戸惑いながらも、だんだんとコツをつかみ笑顔でシミュレーターを楽しんでいました。
2024年5月14日(火)第2回目
JR貨物さまが取り組んでいる
活動内容について学びました。




JR貨物 東海支社さまの施設見学をさせていただいた翌週の2024年5月14日(火)は、本学の長久手キャンパスにJR貨物 東海支社の皆さまがご来校され、営業の野村さまから、改めてJR貨物さまの会社概要や営業の仕組みについてレクチャーしていただきました。学生を飽きさせないようにところどころにクイズを挟むなど、楽しい内容となりました。続いて総務の鹿田さまからは会社が見据える長期ビジョン2030をご紹介していただき、JR貨物さまが社会に提供する「物流生産性の向上」、「安全・安心な物流サービス」、「グリーン社会の実現」、「地域の活性化」といった4つの価値について解説。その中でも4番目の「地域の活性化」について詳細に説明していただきました。というのも、この地域の活性化こそが今回の課題である車両のラッピングデザイン考案につながるからです。その後、質疑応答として学生からは「現状のラッピングは愛知県をモチーフにしていると聞きましたが、どの辺りで感じられますか?」、「カラーが赤色なのはなぜか?」、「デザインを考えるにあたって何をアピールしたいか?」といった疑問が寄せられました。特に最後の質問については「何をアピールしたらいいのかも含め、若い皆さんのアイデアを提案してほしい」と回答いただき、JR貨物の皆さまからの期待度の高さがうかがえました。

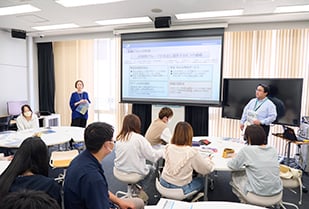
最後に総務の大原さまから今回の復習を兼ねたクイズを出題いただきました。「鉄道はトラックが排出するCO2(二酸化炭素)をどれくらい低減できる?」、「貨物列車で最も多く運んでいる荷物は何?」などの問題を出していただき、鉄道貨物の知識を再認識しました。
2024年5月21日(火)3回目
4つのグループに分かれて、
JR貨物さまや貨物物流の価値について議論しました。


5月21日(火)、今回もJR貨物 東海支社の皆さまにお越しいただき、車両のラッピングデザインを考える上でヒントとなるディスカッションをおこないました。この日はテーマを2つ用意。一つめは「もしこの世に貨物(列車、トラックなど)がなかったら、どうなっているか?」。二つめは「貨物について初めて知ったことは?なぜこれまで知らなかったのか、地域の方に知ってもらうメリットは?」。この2つのテーマについて議論するため、学生たちは4グループに分かれ、それぞれのテーブルにはJR貨物の皆さまにアドバイザーとしてついていただきました。

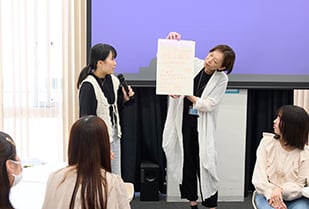
一つめのテーマについて約15分、議論した後、各グループが考えた内容を発表。「自給自足を強いられる」、「モノを買うための移動時間が増える」、「人口が分散し、都市と田舎の格差が軽減する」などの意見が出ました。中には絵日記風に発表するグループもあり、それぞれの個性が発揮される発表でした。


続いて二つめのテーマについても議論。これについては「夜に運行していること」、「環境にいいこと」や「知名度向上によってビジネスチャンスが広がる」、「採用面で有利になる」などの意見が出ました。


5月におこなわれた全3回の授業を振り返り、JR貨物の皆さまからは「想像以上にJR貨物のことを知っていただけた。鋭い質問もあり、驚かされた」、「JR貨物の知名度が低いことを実感。もっと知名度を上げるために皆さんの力を貸してほしい」といった期待の声が聞かれました。
この後、ゼミ生たちは全3回の授業で得た知識を元に車両ラッピングデザインを考案していきます。地域の方々に役に立つ提案をできるよう、力を入れて取り組んでいきます。












