追究
2024年12月13日
ビジネス学部 専門教育科目 「私のシゴト学」第5回~第8回

2024年5月15日(水)~6月5日(水) 星が丘キャンパス55A教室
「働く」とはどういうことか。経験豊かな職業人の方々による講演は、学生たちが将来について考える絶好の機会となりました。
ビジネス学部は、「経営学」、「商学」、「会計学」、「経済学」の4領域を学びの基盤とし、アクティブラーニングを積極的に取り入れながら、ビジネスの現場で活きる知識とスキルを理論と実践の両面から修得していく学部です。3年次に開講される「私のシゴト学」は、社会で活躍されている職業人の方々をお招きし、その体験談などから「シゴトとは何か」、「働くことの意義とはどのようなものか」を学び、就職活動やキャリア設計のヒントとすることを目的としている専門科目です。
以下では、第5回~第8回の講義内容をダイジェストで紹介します。
【第5回】5月15日 株式会社高津製作所 代表取締役社長 髙津晋一 様 他3名様
自動車生産設備の開発・製造をおこなう株式会社高津製作所の代表取締役社長・髙津様は、3名の社員の方々とともに登壇されました。それぞれ異なる立場からこれまでの「変化」についてご講義いただきました。
はじめに髙津様より、「経営者として意識してきた変化」についてお話しいただきました。AI技術の進化によってシンギュラリティ社会(技術進化によりAIの知能が人智を超える社会)の到来が予測されるなか、AIが台頭する社会で人間が活躍するには創造力や思考力が重要になるという観点から、同社では、「夢を世界に届けよう」、「人が人らしく活躍する企業であり続けよう」、「常に学び続けよう」の3点を理念として掲げ、社会の変化に対応しながら成長することをめざしているとお話しいただきました。現代、そして未来の社会において会社がどうあるべきかという視点に立ったお話は、学生にとって、新しい気づきを得られる内容でした。


次に、新卒で入社して3年目の本田様から、ご自身の学生時代から現在までの考え方や気持ちの変化についてお話しいただきました。学生時代の本田様は、「仕事の具体的な想像がつかない」、「慣れない場所で周りの人とうまくやっていけるかわからない」といったさまざまな不安を抱えられていたそうです。しかし、上司や先輩方の優しいサポートもあり、入社後はそのような不安も払拭されたといいます。
現在、人事を担当されている本田様は、「学生が抱く会社や仕事に対するイメージと、実際の社会人生活のギャップをなくしたい」と力強く語ってくださいました。また、就職活動を控える学生たちに「知名度や他人の勧めなどといった“誰かのものさし”ではなく、自分の価値観や将来像を大切にして、“自分のものさし”で企業を選んでほしい」とアドバイスしてくださいました。
続いて、人事戦略室のグループマネージャーとして活躍されている石塚様から、チームを率いてきた経験から生まれた考え方についてお話しいただきました。
チームワークで重要なのは、「個性を認め合う」ことであり、「年齢、性別、性格などが異なる人たちが協力し合うことで、多様性のあるアイデアが生まれる」こと。さらに、変化し続ける社会で生き抜くための考え方として「やらなければならないこと(Must)をこなすことで、できること(Can)が増え、それを繰り返すことで自分のやりたいこと(Will)に手が届くようになる」と、社会人として持つべき意識についてお話しされました。


最後にご登壇いただいた経営企画本部長の宮路様からは、社会人として求められる変化についてお話しいただきました。周囲から求められる人材になるためには、「視野を広く持つこと」「意識を変えること」「行動を起こすこと」の3点が重要であるにもかかわらず、自分自身に対する先入観が変化を妨げ、成長を阻害してしまう場合があること、そしてこの先入観が、就職活動の場においても悪影響を与えうることを力説してくださいました。「第一歩として、何から変化させればよいか」という学生からの質問に対して、「行動を変えること。何でも良いので新しいことに挑戦したり、行ったことのない場所を訪れたりすることによって自分の考えの幅が広がります。」と、取り組みやすいところから「変化」をさせていくことの重要性についてお話しくださいました。
企業内での立場の異なる方々から、ビジネスの現場での意識や社会人に求められる素養などについてお話しいただいたことで、学生の視野は大きく広がり、「シゴトとは何か」を考えるうえで、大きなヒントを得ることができたはずです。
【第6回】5月22日 東海鉄工株式会社 代表取締役社長 小澤佳之 様/製造部板金課 課長 武藤一生 様
第6回は、自動車部品のプレス加工などをおこなう東海鉄工株式会社の代表取締役社長・小澤様と、板金課課長・武藤様にご登壇いただきました。はじめに小澤様より、会社の概要やプレス加工、金属溶接などについて、動画を用いながらご説明いただきました。また、創業から現在までの技術の変遷についても解説していただき、手作業でおこなっていた加工や溶接を自動化したことにより、社員のケガのリスクが下がり、品質や生産性も向上したこともお話しいただきました。
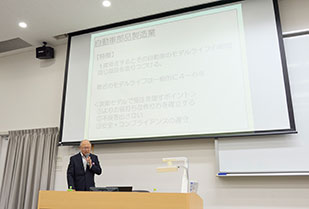

続いて武藤様からは、「社会人に必要なこと」をテーマに、「ビジョン」、「チームワークとコミュニケーション」、「リフレッシュ」の3点についてお話しいただきました。はじめに、「ビジョンを持つことで実行力や行動力が生まれる」ことの大切さについて、「モノづくりコンクールで受賞する」という目標を掲げて励み、優秀賞を受賞したことなどを例に挙げながらご説明くださいました。次に、「チームワークとコミュニケーション」について、過去に新設備を導入した際のトラブルにより、入社以来最大の危機に直面し、心身ともに大きなダメージを負ったものの、全社体制のサポートにより、各専門部署と連携しながら問題に対応しえたことで、無事に解決することができたという経験から、「仕事は一人では達成できない」ことを強く実感したと話されました。最後に、「リフレッシュ」については、心の緩和と強化につながるものとして、学生に対しても、「ポジティブな精神でチャレンジするために、自分なりのリフレッシュ方法を見つけてほしい」とアドバイスの言葉をくださいました。


後半には小澤様が再び登壇され、ご自身が経験した3つの失敗と、それらをどのように乗り越えてきたかについてお話しくださいました。1つ目は、加工費(売値)を原価より低く見積もってしまい、会社として大きな赤字を出してしまったこと。その時は真摯な対応の積み重ねによって危機を脱することができたと振り返られました。さらに、2つ目の失敗では、リスク対応やコンプライアンスに対する意識が高まったこと、3つ目の失敗では、海外事業からの撤退を通して、将来を見据えた社員育成の重要性や事業計画の難しさを痛感したことなどについてお話しいただきました。これらの失敗を乗り越えられたのは、「恵まれた環境」、「良い家庭」、「運の良さ」のおかげであるが、数々の経験から身についた忍耐力があったからこそ、リーマンショックや東日本大震災といった苦難にも打ち勝つことができたと語ってくださいました。
最後に、学生たちへのメッセージとして、「困難は永遠には続かない」という金言とともにお話を締めくくられました。
【第7回】5月29日 オカタ産業株式会社 代表取締役社長 岡田哲士 様
第7回は、モジュールをはじめとした自動車部品を生産するオカタ産業株式会社の代表取締役社長・岡田様にご登壇いただきました。ご自身の経験や、大切にされている目標、仕事を通じて学んだ教訓などについてご講義いただきました。


大学時代から、人生の最後に「よく生きた」と思えるような一生を送ることを目標に掲げていらっしゃったという岡田様にとって、「よく生きること」とは、没頭できる趣味などを見つけて「個人として充実すること」と、自分に最適な職場環境で社会的意義のある仕事をして「社会人として充実すること」の両立によるものとのこと。特に、「最適な職場環境」を重視し、仕事の内容や進め方などに自分の意思が反映できる環境で働くことを希望され、大学卒業後はベンチャー企業に就職。会社規模は大きくはないものの、それゆえに経営者と近い距離で接することができ、トップのあり方や従業員との接し方、資金繰りの難しさなどについて、間近で勉強することができたと話してくださいました。


この他にも、ベンチャー企業での経験から、後の人生に大きな影響を受けたとおっしゃいます。管理部門で仕事をされていた岡田様は、希望と異なる営業部に異動となった際に、仕事へのモチベーションが下がってしまったことがあったとのこと。しかし、上司からプレゼンテーションのコツや目標設定の方法などを、細かく丁寧に教えてもらったことにより、営業の現場でも成果を上げることができるようになり、仕事を楽しめるようになったそうです。営業部での成績が上がってきた矢先、今度は人事総務部への異動が決まり、自分の中で折り合いがつけられないまま仕事をするということもあったものの、さまざまな部門や部署で培ったスキルは現在の社長業でとても役立っているとおっしゃいます。「人生何が幸いするかわからない。自分の意にそぐわないことでも、一所懸命に取り組めばその経験が役立つときが来ます。」と、数々の経験から得た教訓を、学生たちにも熱く語ってくださいました。
【第8回】6月5日 東濃信用金庫 常務理事 土屋博義 様
2024年度の「私のシゴト学」最終回は、東濃信用金庫の常務・土屋様にご登壇いただきました。新入社員として信用金庫に勤めてから、これまでの長い“金融マン”人生を振り返りながら、ご自身の仕事に対する意識や情熱などについて、お話しくださいました。


就職活動開始当初はメーカーへの入社を希望し、内定も得ていたとのこと。しかし、就職活動を続けるうちに、金融業、特に信用金庫に強い興味を抱くようになり、最終的にはメーカーの内定を辞退することを決め、謝罪のためにその会社を訪問したそうです。就職活動が今よりもはるかに厳しい時代、対面した人事担当者は怒りをあらわにしながらも、電話や書面ではなく、直接、謝罪にやってきた土屋様に、厳しくも優しい言葉をかけてくれ、その時の記憶が今も鮮明に心に残り、土屋様の力になっていると話してくださいました。
新入社員として東濃信用金庫に勤めることになった土屋様は、厳しいことで知られる支店に配属され、当初は苦難の連続ながらも、そのような状況下でも同僚と励まし合ったり、取引先にフォローしてもらったりしながら、少しずつ経験を積んできたと振り返られました。
仕事に対する意識が明確に変わったのは、あるお客様との出会いがきっかけだったと話されます。仕事に対するモチベーションを失いかけていた時期のこと。取引先を訪問し、細かな作業をしている最中、小さなお子さんがキャッキャとはしゃぎ回っていたことに、疲れや焦りから思わず声を上げそうになったとき、お客様から一枚の絵を見せられたそうです。「うちの子、“大好きな人”の絵を描けと言われて、『とーのーさん!』と土屋さんの絵を描いたのよ。」と、手渡されたその絵を見た時、土屋様はご自身が「東濃信用金庫」を背負ってお客様とお会いしていること、そして、「東濃信用金庫」やご自身が多くの方に支えられていることを実感。その後は心機一転、お客様との出会いを大切にしながら真摯に仕事に取り組むようになったと振り返られました。
熱心な仕事ぶりが評価され、次長(管理職)に昇進した土屋様でしたが、当初は慣れない業務に悪戦苦闘されたとのことでした。しかし上司から、「周りの人のサポートに甘えることも大切だ」と教えられたことで、上司や同僚だけでなく、部下とも協力し合いながら仕事を遂行できるようになったとお話しくださいました。支店長に昇進後しばらくの間は、ご自身の若い頃の経験から部下に厳しく接していたにもかかわらず、社員旅行の際には部下たちが揃って誕生日のお祝いをしてくれ、「お互いに体に気をつけて、より良い仕事をしましょう」という思いやりの言葉に、思わず涙を流してしまったことも話してくださいました。


最後に、新入職員に期待することとして、「礼節を重んじること」、「素直であること」、「夢を諦めないこと」などを挙げられ、学生にもそうした姿勢を大切にしてほしいとお話しされるとともに、「ビジネス社会は人を大きくしてくれる。これから社会への一歩を踏み出す皆さんの人生が希望に満ち溢れるものになることを心から願っています。」と、温かなメッセージを送ってくださいました。












