追究
2025年10月14日
愛知淑徳大学 開学50周年記念「違いを共に生きる」書評大賞

2025年7月15日(火)長久手キャンパス図書館
2025年7月23日(水)星が丘キャンパス図書館
第27回 図書館〈書評〉大賞に
55編の応募から9名の学生が選ばれ、
授賞式がおこなわれました。
2025年7月15日(火)に長久手キャンパス 図書館、7月23日(水)に星が丘キャンパス 図書館にて、第27回 書評大賞の授賞式がおこなわれました。書評大賞は、質・量ともに優れた本学の図書館資料をより有効に活用し、本学学生の文化的・知的活動のさらなる発展、批評能力・文章作成能力の向上を通して教育の質的充実に貢献することを目的に創設され、年に2回開催されています。今回は本学の開学50周年を記念して「違いを共に生きる」書評大賞と題し、特別賞として「違いを共に生きる特別賞」が設けられました。
55作品の応募があった今回。授賞式では三和義秀図書館長が「2011年から続く書評大賞では、年々、学生たちの批評の質や文章作成の能力の向上を実感しています」と挨拶し、賞状・副賞の授与へと移りました。






賞状・副賞の授与と、受賞者のコメントの後は、選考委員の先生方からコメントをいただきました。増井典夫先生は「どの作品も甲乙つけ難く、選考に悩みました。私も書評を通じてさまざまな作品に出会うことができました。これからも書評に挑戦してほしいと思います。」と述べられました。


大賞&特別賞

人間情報学部 感性工学専攻2年
伊藤悠芳さん
「『聞く』力」
1年生の時から図書館の学生サポーターに参加し、書評大賞を掲載するLib.letという図書館広報誌の編集にも携わっています。Lib.letに掲載された書評を読んで「この本を読んでみたい」と思うことが多々ありました。私も自分が良いと思った作品を他の人たちにも伝えたいと思い、応募しました。紹介したミヒャエル・エンデ著『モモ』をぜひ多くの人に読んでもらいたいと思います。
準大賞
文学部 国文学科3年
稲葉楓果さん
「『多様性』が生み出す排除」
50周年記念という節目に受賞ができ、嬉しく思っています。朝井リョウ著『正欲』は「違いを共に生きる」という明るいテーマの中でも、比較的、ネガティブに捉えている視点に読み応えを感じて、書評にまとめました。

心理学部1年
武藤真帆さん
「理解したつもりの傲慢さ」
大学生になってさまざまな方と接して、自分なりに「多様性」を理解していたつもりでしたが、朝井リョウ著『正欲』を読んで、多様性をわかった気になっていることは怖いなと感じました。書評を読んで、少数派=「理解されたい人」ではないということ、「少数派だから受け入れなければならない」というわけではないこと、自分が受入れる側だと思い込んでしまっている人がいることを、知ってもらえたらいいなと思います。
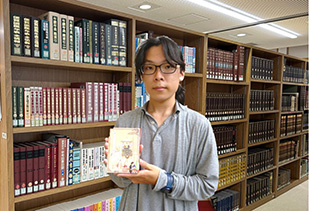
創造表現学部 創作表現専攻3年
林和槻さん
「アジアの視座発見のための鏡」
西洋対日本というイメージ、あるいは自分は地球人であるという意識はだいぶ浸透したと思うが、「自分はアジア人だ」という意識はあまり浸透していないと思います。「違いを共に生きる」ためには、まずは自分のことを知らなければと思い、谷崎由依著『鏡のなかのアジア』を選びました。
佳作

文学部 国文学科2年
水村美緑さん
「愛しみの秘儀」
若松英輔著『悲しみの秘義』を読みました。大切な人のことを想って悲しいとき、どうしたらいいんだろう。この本は、そんな問いの痛みが、「愛(かな)しみ」を感じられる出会いにおける宝物の感情であることを教えてくれました。そして、私にこんなにも幸せな問いを与えてくれたのは、図書館を支えてくださっている職員のみなさま、高校や大学で出会った先生方や友人です。毎日、心から感謝しています。
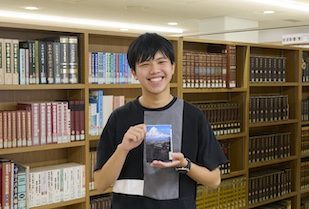
人間情報学部 感性工学専攻1年
廣村壮太郎さん
「不幸せに慣れないで」
私が読んだのは三秋縋著『三日間の幸福』で、1年につき1万円で寿命を売り払ってしまうというお話です。1年に1万円と聞くと安いなと思ってしまいます。主人公も安いと感じたのですが、人生に前向きでなかったため3ヶ月を残して、寿命を全て売り払ってしまいます。3ヶ月の余生の中で、幸福を見つけるというのが、本のテーマです。タイトルだけでも心に残していただけたら嬉しいですし、読んでいただけたら、とても光栄です。
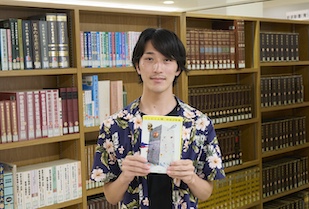
創造表現学部 創作表現専攻3年
横井俊介さん
「個性とは何か」
1年生の頃から書評大賞が気になっていましたが、なかなか応募することができずにいました。昨年冬に受けた授業で学んだことを活かそうと思い、今回応募しました。選んだ本は村田沙耶香著『コンビニ人間』です。授業の単位も取れて、賞もいただき、大変嬉しかったです。みなさんにもチャレンジしてもらいたいと思います。
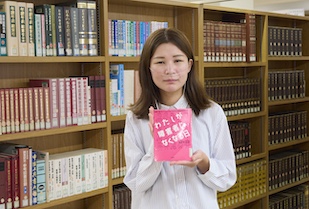
創造表現学部 メディアプロデュース専攻1年
山下美緒さん
「障害とともに」
大学生になり新しいことに挑戦してみたいという思いがあり、応募しました。海老原宏美著『わたしが障害者じゃなくなる日』を、私自身の生活と重ねて読み進めました。私がいろいろ挑戦している時に、現実とのギャップを感じ、少しモヤモヤとした気持ちになることがあります。この本はそうしたモヤモヤが少し晴れるような内容でした。書く難しさを感じましたが、とても貴重な体験になりました。

交流文化学部 国際交流・観光専攻4年
脇山結月さん
「『知ること』の先にあるもの」
ダニエル・キイス著『アルジャーノンに花束を』について書きました。ちょうど就職活動を終えて、社会に出ようとしている自分の状況と、この本に描かれている成長や人としてどう生きるかというテーマが重なって、共感しながら書きました。知能や能力だけではなく、人との関わりの中に大切なものがある、そんな思いを自分の経験と重ねて文章に込めました。受賞は、就職活動や今までの書評大賞で努力してきたことが報われたような気がして、とても嬉しく思っています。












