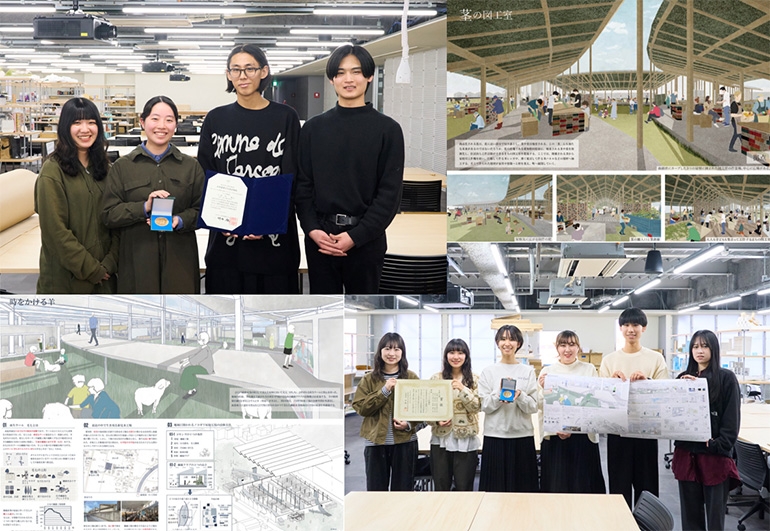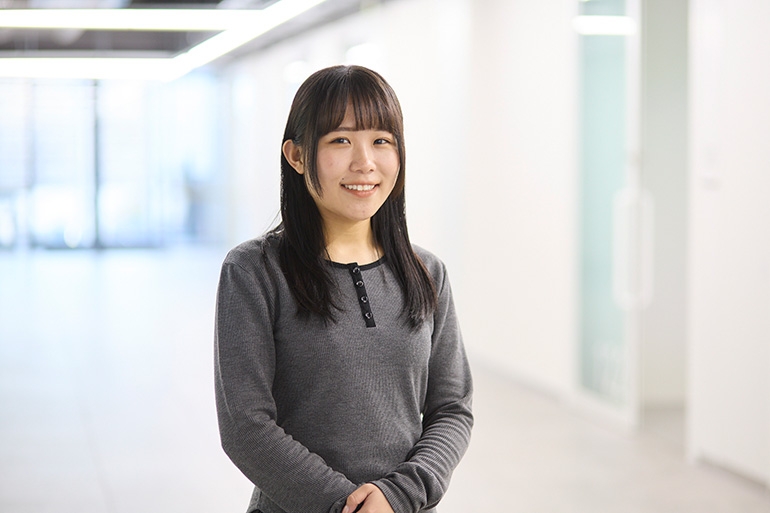躍動
2013年03月21日
マレーシアの小さな村で、ボランティア活動を経験。村体験は衝撃でした!

vol.08

日本とは違う豊かさを教えてくれたマレーシアでのワークキャンプ
 夏休みを利用して、マレーシアで植林や農作業、ホームステイを行う2週間のワークキャンプに参加しました。きっかけは海外でのボランティア活動に挑戦してみようと、大学のコミュニティ・コラボレーションセンター(CCC)を訪ねたことです。閲覧した数々の資料の中に、私が以前インターンシップでお世話になったNGOが主催する今回の企画を見つけたので、安心して参加を決意することができました。
夏休みを利用して、マレーシアで植林や農作業、ホームステイを行う2週間のワークキャンプに参加しました。きっかけは海外でのボランティア活動に挑戦してみようと、大学のコミュニティ・コラボレーションセンター(CCC)を訪ねたことです。閲覧した数々の資料の中に、私が以前インターンシップでお世話になったNGOが主催する今回の企画を見つけたので、安心して参加を決意することができました。
もっとも印象的だったのは、ティウロン村という、わずか12家族の小さな村でホームステイをしたことです。水道も電気も通っておらず、たまに降る雨だけが頼りの村です。日本のようなお風呂がないことはもちろん、村の人たちは洗濯なども茶色に濁る池で行っていました。また、村には仕事がないため、青年たちのほとんどがほかの土地へと出稼ぎに出てしまい、働き盛りの人がいません。日本で暮らしていると想像も経験もできないことの連続で、村には生活面の問題が山積みのように思えました。私たちはホームステイをしながら植林や荒れた森の草刈りなどをお手伝いし、さらに、水不足や人手不足の解消を少しでも図ってもらうために雨水を貯めるためのタンクを12本と、成長すれば収入源になるゴムの木の苗1,200本を贈りました。
「でも、こんな小さなことで本当に意味があるのだろうか」。そんな疑問が何度も浮かびましたが、満足のいく正解は最後まで見つけだすことができませんでした。しかし、村の皆さんは過酷な暮らしに屈することなく、どんなときもおおらかに過ごしていました。言葉が通じない私たちに優しく接してくれたことは深く印象に残っています。子どもたちと池で水浴びをしたり、歌を歌ったりしてふれあったことも良い思い出となりました。子どもたちの笑顔ときらきらとした目は一生忘れることがないでしょう。ボランティア活動に取り組みながら村の人たちと暮らしをともにすることで、日本とはまた違う心の豊かさを実感できたのは大きな収穫でした

初めてのボランティア活動は1年生のとき。それ以来、幅広い活動に楽しく取り組んでいます。
 私がボランティア活動や環境問題に興味を持ったのは、高校生のころです。しかし、何から始めれば良いのかまったく分からず、本格的に取り組むようになったのは大学生になってからでした。授業で国際問題や社会問題などを学んでいくうちに、まずは自分なりに行動してみようという気持ちが明確になっていったのです。
私がボランティア活動や環境問題に興味を持ったのは、高校生のころです。しかし、何から始めれば良いのかまったく分からず、本格的に取り組むようになったのは大学生になってからでした。授業で国際問題や社会問題などを学んでいくうちに、まずは自分なりに行動してみようという気持ちが明確になっていったのです。
初めてボランティア活動に参加したのは、1年生のときです。愛知万博に出展されていたあるNPOのブースをお手伝いしたことを皮切りに、大学での学びや人との出会いを通じて、幅広い活動に取り組むようになりました。現在はOSHARECO(おしゃれこ)という団体にも所属し、マイボトルやマイ箸が利用できるカフェやレストランを記載した地図を作成しました。ボランティアやエコロジー活動に参加することは、今では私のライフスタイルの大部分を占めており、趣味のように夢中になっています。
今回のマレーシアでのワークキャンプには、17歳の高校生から64歳の方まで幅広いメンバーが集いました。年齢も職業も異なる方々と活動をともにし、深く議論した経験からは学んだことも多く、ほかでは得がたい貴重な機会になりました。私も生涯を通してボランティアなどの活動を続けていきたいと考えています。