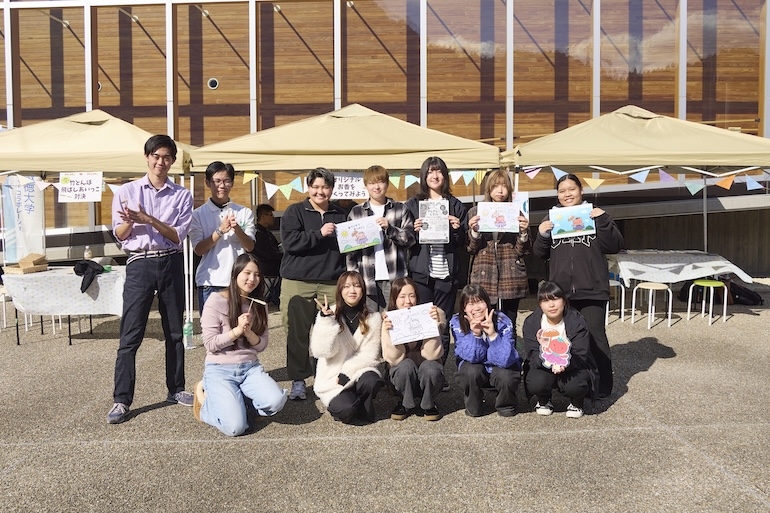交流
2025年03月25日
日進市制30周年記念 提案型大学連携協働事業 ~パネルディスカッション~ 障がいのある人と一緒に考える未来の街づくり
2024年度 健康医療科学部 展示会・講演会・発表会 福祉貢献学部

2025年1月10日(金) 日進市中央福祉センター
障がい者への理解を深め、共に生きぬくまちづくりのために。
講演・パネルディスカッションが開催されました。
1⽉10⽇(⾦)⽇進市中央福祉センターにて、⽇進市制30周年を記念した⼤学連携協働事業の一環として、障がいのある⼈と⼀緒に考える未来の街づくり」をテーマにした講演とパネルディスカッションが開催されました。
愛知淑徳大学は、日進市が取り組む日進市大学連携協働事業の1つである「障害理解に関する周知啓発事業」に関わっており、今回のパネルディスカッションの第一部では、本学の福祉貢献学部の瀧誠教授が登壇しました。
瀧先生は障がい者の権利擁護を専門としており、名古屋市障害者施策推進協議会委員、日進市障害者政策委員会の前委員でもあります。地域における障がい者福祉の動向に深く関わっており、福祉ビジネスと公民の二つの視点から障がい者のアドボカシー(権利擁護)をどのように進めていくかをお話しいただきました。


瀧先⽣の講演では、はじめに「障がいのある⼈から学ぶこと」と題して、障がいのある⽅と共に過ごし、コミュニケーションを取ることにより、どのような場⾯で⽣活の困難さや⽣きづらさを感じているのか、五感を使って知ることの重要性を伝えてくださいました。そこでは知的障がいのあるお子さんを抱える親⼦のドキュメンタリー映像が上映され、訪れた⽅々は映像に映し出された切実な苦悩を感じとりながら、⾃分達ができることを考えているご様⼦でした。
その後先生は⽇進市がどのような取り組みを行なっているかを紹介してくださいました。また、⽇進市が掲げる基本理念「地域で 共に暮らす まちづくり」に込められた考え⽅を具体的に説明しながら、⽇進市は連絡会などのピア活動が盛んで、障がいのある方々が⾃分たちの意⾒を伝えやすく、また個々の⽀援者に⼿が届きやすい環境である点を⾼く評価しました。⼀⽅、⼤都市に⽐べ危機管理体制などまだ十分着⼿に及んでいない部分もあると指摘し、これからの発展に期待すると仰っていました。
その上で、障がいのある方の理解をすすめる上での留意点などを伝え、専⾨家だけはアドボカシーの主体にはなり得ず、市⺠が⾝近な隣⼈となれるよう「ピアアドバカシー(同じ問題を抱える仲間同⼠が互いのニードを代弁)」「セルフアドボカシー(⾃ら権利を主張する)」「シチズンアドボカシー(市⺠が主体となって援護する)」の観点から、権利擁護活動を提案しました。


後半では、本学の健康医療科学部の⾥中綾⼦教授が座⻑となり、障がいを抱えるお⼆⼈を交えたパネルディスカッションが開催されました。パネリストとして登壇したのは森美親さんと豊⽥優さんのお⼆⼈。森さんは周囲の反対を受けながらも同じ脳性⿇痺の障がいを持つ⼥性と結婚し、福祉サポートや福祉機器などを活⽤しながら結婚⽣活を送っています。豊⽥さんは26歳から⼀⼈暮らしをはじめ、現在は福祉施設で事務職員として勤務する傍ら、⾞いすダンス「名古屋ビバーチェ」の代表を務めています。


パネルディスカッションでは障がいのある⽅がどのように⽣活されているか、お⼆⼈からリアルな⽇常をお伺いしました。森さんはヘルパーなどの介護を活⽤しながら、⼀緒にスーパーマーケットに買い物に行くこともあるそうで、豊⽥さんは住まいの近くにスーパーマーケットやコンビニエンスストアが揃っていることからさほど暮らしに不便を感じていないと仰っていました。その他、バリアフリーの住まいの様⼦や外国⼈の介護者が増えている実情にも話が及び、障がいを持つ⽅がどのように感じているか、参加された皆さんもお⼆⼈の⾔葉に⽿を傾けていました。
⽇進市は若い世代が多いエリアですが、30年もすれば⾼齢化が進んで行きます。パネルディスカッションにも参加した瀧先⽣が「そうした未来も予測しながら、お互いが助け合えるように地域を集約したコンパクトシティの実現が望まれる」と仰ると、豊⽥さんは「私が今住んでいるところは駅から3分のところですが、⼩牧市にある実家は歩いて10分以上はかかってしまう。おそらくそれ以上かかる⼈もいるでしょう」と障がいのある方や⾼齢者にとっては暮らしにくいエリアがあることを具体的にお示しになりました。また、災害などのリスクに備えるためにも、地域に住む⼈たちのコミュニケーションは⽋かせないという点では来場者の全員がうなづきながら「⼈に関⼼を持つことの⼤切さ」についても熱心な議論が交わされました。

本学では、今後もこうした連携協働により、日進市だけでなく広く社会と関わって、課題解決に取り組んでいきたいと考えています。