交流
2016年04月11日
チャレンジファンド2015 最終報告会
2015年度 地域・ボランティア活動 展示会・講演会・発表会

平成28年3月17日(木) 星が丘キャンパス 午前:13B・13C教室 午後:アクティブ・ラーニングスタジオ
チャレンジファンドが支援した15の団体が、約一年間の活動結果を報告。
お互いの成果や成長プロセスを分かち合いました。
愛知淑徳大学では、学生が運営する多くの自主活動グループがあり、社会との連携を積極的に深めています。その活動を支える愛知淑徳大学の教育機関が「コミュニティ・コラボレーションセンター(CCC)」。ボランティア活動の紹介や自主活動のサポートをはじめ、学生たちの社会貢献活動に対し、資金面で援助をする制度「チャレンジファンド」も用意しています。昨年6月におこなわれたコンペで、15団体の活動が社会的に意義のあるものと認められ、支援を受けました。各団体とも、自分たちで立ち上げたプロジェクトを精力的に進め、約一年間の活動を完走。その集大成となる「チャレンジファンド2015 最終報告会」が3月17日(木)に星が丘キャンパスにておこなわれました。
午前の部では、地域福祉や環境活動などテーマごとに15の団体が2つの教室に分かれ、活動の成果を報告しました。その内容は、今年度のプロジェクトの概要説明、活動成果、反省点など。活動風景の写真や図表をスクリーンに映し出しながら、与えられた10分間の発表時間いっぱいに、いきいきと活動の様子を伝えました。その後、各学部の教員で構成されたCCC運営委員からの質問にも堂々と答えていきました。運営委員からは「イベント参加者数を前回と比較できるよう数値化し、わかりやすい」「目に見える成果があると自信につながる」「自主的に勉強会をしている点がすばらしい」と、活動に対する評価の他にも、するどい指摘や改善点など、さまざまなアドバイスが送られました。学生たちはそれらの意見を真摯に受け止め、次年度の活動へ決意を新たにしていました。
すべての発表が終了すると、参加学生と運営委員は「社会貢献性」「チャレンジ性」「計画の妥当性」「継続発展性」の4つの採点基準に対して、それぞれが評価する団体へ投票をおこないました。


午後の部は、アクティブ・ラーニングスタジオに場所を変え、各団体が活動から学んだことを共有するために、交流会がおこなわれました。
プログラム
(1)各教室から1団体ずつ報告
(2)失敗経験から学ぶワーク 危機一髪エピソード
(3)「明日からこうしたい!」フリップ宣言
(4)センター長より全体講評
はじめに、午前の発表で運営委員からの評価が高かった「ASU element project」と「コミュカフェ」が改めて成果報告をしました。両団体の発表後には、2~3の団体に分かれた各テーブルで、グループワークを実施。まずは、25分の自己紹介タイムがあり、その後「危機一髪エピソードと、そのリカバリー方法」を各テーブルの代表団体が発表しました。「団体内でモチベーションの差ができてしまった。共通意識をもつことができるよう、ミーティングでの情報共有や現場の視察を大切にした」「スケジュール管理がうまくできない場面があった。その反省を生かして、プロジェクトを前倒し、且つ協力団体に相談しながら進めるようにしたところ、相乗効果でよりよい成果を生むことができた」など、さまざまなエピソードが語られ、学生たちは今後の活動の参考のために、熱心に耳を傾けていました。
グループワークの最後には交流会のまとめとして「明日から○○○したい」宣言を、一人ひとりがフリップを掲げ、参加者全員に向かって堂々と発表しました。「前倒しで準備をしていきたい」「スケジュール管理をしっかりする」など、次年度の活動に向けた抱負から「ダイエットしたい」「笑顔で一日を過ごしたい」など、プライベートな内容もあり、会場は大いに盛り上がりました。
最終報告会の最後には、15団体の活動を支え続けてきたCCCのスタッフがあいさつをしました。「困ったらすぐに相談してください」「どんな問題が起きても、みんなで知恵を出し合い、リカバリーしていきましょう」と心強い応援メッセージが送られました。さらに、CCCセンター長であるビジネス学部・大塚英揮教授からは「お金をいただいて活動するということは、責任を伴い、結果を残さなければなりません。このような貴重な経験をした皆さんは、この一年間で大きく成長しました。発表では自分の言葉として皆さんがしっかりと語っていると感じました。今後も皆さんが実りある活動ができるようCCCはサポートしていきますので、大いに活用してください」と有意義な時間を締めくくりました。


愛知淑徳大学の学生たちの社会貢献活動に対して協力団体・企業・教育機関からの評価は高く、期待された存在です。また、市の広報誌や、ローカルテレビなどの取材依頼も増え、注目が集まっています。学生たちは、その期待に応えるためにも全力でサポートするCCCと手を携え、今後も力強く取り組んでいくことでしょう。
各団体のプレゼンテーション(一部抜粋)
ASU element project
「まなぼう!ひらこう!あゆもう!英語で広がる世界」
「小学校の英語教育を支え、一人でも多く子どもたちが英語に親しむ」をプロジェクトテーマに活動しています。2015年度は小学校に訪問し、ALT(外国語指導助手)の授業サポートや、アメリカ・日本の小学校間での「お手紙交換プロジェクト」を実施しました。また、地域で英語を楽しむゲームイベント「えいごであそび隊」も開催。子どもたちが楽しく英語にふれあうお手伝いをする中で、「学生が来ると、子どもたちのやる気がアップする」という声もいただき、運営する私たちも自信や行動する大切さを得ることができました。


コミュカフェ
「“やさしいところ”をみんなのおばあちゃんの家にしようプロジェクト」
災害時に地域で助け合いができる関係づくりをめざし、着目したのが「多世代交流」。そこで、多くの人びとが関われる場所をつくりたいとデイサービスセンター「やさしいところ」で交流会「コミュカフェ」を運営しました。ここでは私たちが季節のイベントやクッキーづくりなどさまざまな企画を毎月展開。デイサービスを活用する高齢者の方々や近所に住むご家族など、さまざまな人にご参加いただき、たくさんの笑顔を引き出すことができました。今後は地域の方々同士が関わりあえるイベントも展開できればと考えています。

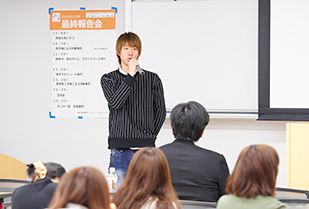
その他チャレンジファンド採択団体
すーみるきぃ
「BOOKS HONEY」

読書会で笠寺商店街の活性化をめざす
travelD
「円頓寺商店街×訪日外国人MAP」

訪日外国人向け商店街MAPづくり
エコのつぼみ
「竹炭消臭剤~里山を守ろう~」

里山保全活動を支援し、市民へ向けた環境啓発
アウトドアレストラン
「The farm house」

農家の思いを消費者に届け、食への意識向上をはかる
大学祭実行委員会
「三世代で地域交流」

一緒に工作をして三世代の交流を深める
生きている図書館準備委員会
「生きている図書館2015」

ゲストスピーカーを「本」に見立てると」いう、社会から偏見をなくすための新たなアプローチ方法
ボランティアサークルあじゅあす
「あじゅあすの余暇支援」

高齢者や障がい者の余暇活動の充実を手伝う
共同料理なごやか
「“食”から広がるつながり&健康」

食を通して健康づくりや交流を進める
にじいろあーす
「多文化共生プロジェクト
~強くなる世界~」

外国人児童と交流し、多文化の理解から共生をめざす
☆キャンウインドアンサンブル
「世代を超えた交流
~☆キャンプロジェクト~」

吹奏楽の演奏活動でコミュニケーションの活性化
Fsus4
「音楽を通して広がる関わりの輪」

演奏を通して異なる世代の理解を深める
アミーゴ
「こども応援団」

日本在住の外国人児童と活動を共にし、彼らの夢と希望を叶えるお手伝い
ちびっこクローバーズ
「子どもが行う、子どもだけの街づくり
『クローバーズタウン』開催」

模擬タウンづくりから子どもたちの自主性と協調性を育む












