追究
2024年09月19日
第25回 図書館<書評>大賞

2024年7月16日(火)長久手キャンパス図書館
2024年7月24日(水)星が丘キャンパス図書館
9名の学生が選ばれ、図書館<書評>大賞の授賞式がおこなわれました。
2024年7月16日、17日に長久手キャンパスの図書館で、7月24日に星が丘キャンパスの図書館で、第25回図書館<書評>大賞の授賞式がおこなわれました。<書評>大賞とは、質・量ともに優れた本学の図書館資料をより有効に活用し、本学学生の文化的・知的活動のさらなる発展、批評能力・文章作成能力の向上を通して教育の質的充実に貢献することを目的に創設され、年に2回開催されています。


今回は56名の応募者から9名が受賞。授賞式の冒頭では図書館長から「大学生の読書調査を見ていると半分の割合で読書離れが起きているという結果を示しているが、皆さんの書評を読ませていただくとさまざまな視点から書かれ、それらの書評はきっと多くの学生に読書の魅力を伝えていくのだと思います」と述べられ、大賞受賞者には賞状が手渡されました。






選考委員の増井先生からは「どれも力作揃いでした。書評は人にうまく伝わるよう書かないといけないのが難しいところ。これからも色々な作品を読んで、人に伝わるような文章を書くことを続けていってもらいたいです」とのお言葉が、松田先生からは「昨今の文章創作ではChatGPTが避けられない状況ですが、そういった生成AIは個性がありません。書評はレポートや感想文とは違い、読み手を惹きつけないといけない一方で、客観性がないといけません。すごく難しいと思いますが、皆さんの書評は奥から個性がにじみ出てくるような文章で、読んでいて心地よかったです」とのメッセージをいただきました。
以下では、受賞者からのコメントを紹介します。
大賞
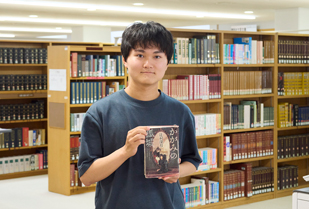
文学部教育学科1年
長谷 海さん
「生きづらさを感じているあなたへ」
辻村深月著『かがみの孤城』を初めて読んだのは高校1年生のときです。すごく感動して勇気づけられたのを鮮明に覚えています。そんな自分にとって大好きな本で、このような素晴らしい機会をいただけたことに感謝しています。ありがとうございました。
準大賞

文学部国文学科1年
井坂 夏菜子さん
「古典文学を読みたくないそこのあなたへ」
私は文学がとても好きですが、最近は理系科目が大事といわれています。駒井稔+「光文社古典新訳文庫」編集部編著『文学こそ最高の教養である』を目にしたときに、私が思っていることを代弁してくれていそう!と思い、読んでみました。図書館もとても好きで、自分の生きる場所です。そんな図書館を舞台にこのような賞をいただけてうれしいです。
文学部国文学科2年 稲葉 楓果さん
「不平等が分断する世界」
川上未映子著『黄色い家:sister in yellow』は1年生のときに読んだ本ですが、その時は主人公たちに感情移入しすぎてうまく書評にまとめられませんでした。2年生になって改めて客観的に読んでみて、自分の思ったことや自分がどうして主人公たちに感情移入したのかを書評に残したいと思いました。書評は好きなので、また機会があれば挑戦したいです。
創造表現学部創造表現学科3年 淀 葉月さん
「事実と真実」
凪良ゆうさんの別作品を以前読んで心理描写にとても感動し、『流浪の月』を図書館で借りて初めて読みました。こんなに素敵な作品を自分の言葉で表現していいのか悩みましたが、現在、小説の書評をするゼミに入っていて、先生に背中を押してもらい、挑戦してみました。これからもこういった素晴らしい賞をいただけるよう、たくさん書評に挑戦していきたいです。
佳作

文学部国文学科2年
川端 咲歩さん
「生きることのパラドックス」
東野圭吾著『パラドックス13』は友人におすすめされて選んだ本です。今回書評を書くにあたり、自分の感じたことや伝えたいことをどのようにしたら読み手に伝えられるだろうということを考え、言葉にすることの難しさを改めて実感しました。書評をきっかけに多くの方にこの本を読んでいただきたいです。

文学部教育学科1年
蟹 結芽さん
「大切な人に『いってきます』が言えるように」
辻村深月著『島はぼくらと』を読み、大学生にこそ読んでほしい、愛知淑徳大学の学生の皆さんにおすすめしたい、という気持ちで書評を書きました。誰かの本を手に取るきっかけになるような書評であれたらいいなと願っています。
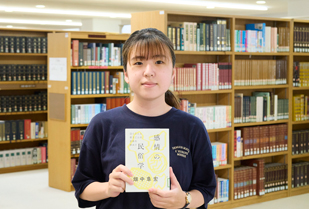
心理学部心理学科1年
野田 和里さん
「『微笑み』に隠された感情」
畑中章宏著『感情の民俗学:泣くことと笑うことの正体を求めて』は書評を書くにあたって初めて読みました。感情についていろんなテーマで書かれている本。テーマごとに1~2ページで読めるので、目次で気になったテーマから読むのもおすすめです。皆さん、ぜひ読んでみてください。
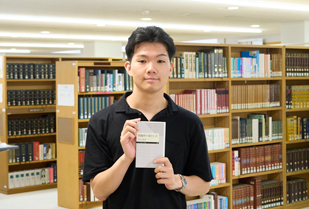
創造表現学部創造表現学科4年
山本 修平さん
「客観性に浸食された私たち」
今の時代はデータや他人がどう思っているかが重要視されますが、村上靖彦著『客観性の落とし穴』には、自分の思いや経験が大事なのではないかということが書かれていて、気付きがあるのではと思って選びました。これまでの書評大賞では物語を題材に選ぶことが多かったのですが、今回、何かを論じた本でも客観性と主観性をもって書評が書けることを強く感じ、自分の言葉で伝える楽しみを味わえました。

交流文化学部交流文化学科4年
丹羽 栞暖さん
「挑戦を続けることの大切さ」
普段はあまり本に触れ合う機会がなかったのですが、スペンサー・ジョンソン著『チーズはどこへ消えた?』は短編小説でストーリーの組み立てがわかりやすく、いろんな登場人物の立場になって考えることで挑戦することの大切さが学べる素敵な本です。メジャーリーグで活躍している大谷翔平選手の愛読書としても有名です。ぜひ皆さんも読んでいただければと思います。












