追究
2024年10月25日
交流文化学部 交流文化概論「防災について」
2024年度 交流文化学部 地域・ボランティア活動 展示会・講演会・発表会

2024年7月29日(月) 星ヶ丘キャンパス 2号館講堂
外部講師を招き、自然災害と避難生活についての講演会を開催。
自然災害が起きたときの行動や
大切な人と事前に話しておきたいことについて考える機会になりました。
交流文化学部では、国籍や文化などさまざまな違いを超え、多様な価値観を認め合える人材の育成に取り組んでいます。
2024年7月29日、災害対策や被災のサポートを行っている認定特定非営利活動法人「レスキューストックヤード」の栗田 暢之様を講師にお招きし、震災や避難所生活についてご講演いただきました。
始めに栗田さんより「災害リスクは誰も逃れられない問題です。南海トラフ地震など起きることが想定される災害に対して備えるという問題ではなく、自分自身がどう向き合うかです」とお話がありました。



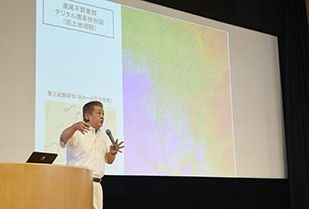
続けて、デジタル標高地形図をもとに地形の高低差、土壌の作りについて学び、今後起こり得る災害について理解を深めます。名古屋市の洪水ハザードマップも紹介いただき、水災が起こりやすい地域について学びました。栗田さんは、「水害の危険性はあらかじめ予想することができます。自宅にいることを想定して、水害についての情報を取得する必要があり、ハザードマップで地域の被害予測を確認し、複数の避難場所を考えておきましょう。そして、必ず家族の方と共有しておいてください。」とお話されました。また、気象庁が発表している洪水警報の危険度分布「洪水キキクル」も教えていただきました。栗田さんは、「高齢者の方はスマホで情報をうまく入手できない可能性があります。皆さんがそういった方に声をかけて、情報を届けてくれるとうれしいです」と学生たちに語りかけられました。


話題は地震に変わり、東日本大震災で被災した女性の手紙を取り上げ、地震が起きたときにすべきことについてもお話いただきました。安否を伝える手段として「災害用伝言ダイヤル(171)」があり、災害発生に備えて体験利用ができることを紹介されました。また、災害が起きてしまった時、避難時の劣悪な環境から「災害関連死」を迎えてしまう人が多いことや、言語の問題でコミュニケーションが取れず適切な支援が受けられないことなど、実際に現場に行かないと分からない被災地での問題についても理解を深める時間となりました。栗田さんは「避難生活をどう支えるかはとても難しい問題です。被災した人が『助けて』とも言いづらい環境です。皆さんには“気づく・整える・つなぐ力”のある伴奏者になってほしいです」と締めくくられました。
栗田さんのお話は、学生たちにとって、自然災害が起きる前に知っておきたいこと、起きたときに行動すべきことを考える貴重な機会となったことでしょう。本学ではこれからも自身で考え、行動できるように学びの機会を提供し、サポートしていきます。












