追究
2024年10月21日
食健康科学部 食創造科学科 高校生のための1日体験講座 おいしさを科学する食品開発の世界
2024年度 展示会・講演会・発表会 進路・就職 食健康科学部

2024年8月22日(木) 長久手キャンパス 1号棟3階134教室
食品開発についてどんなことを学ぶのか?
高校生たちに食品開発の魅力や
本学の充実した施設を伝えました。
2024年4月に設置された食健康科学部 食創造科学科は、食について幅広く学べる新たな学科です。食品学、栄養学、調理学、健康学、食文化、食創生の6領域に関する知識を身につけるだけでなく、食品分析、食品加工、食品開発などを実践的に学び、食産業・食文化の創造や、人々が健康的に過ごせる社会の実現に貢献できる人材を育成します。今回、本学科でどのようなことを学べるのかを高校生の皆さんに知っていただくために、1日体験講座を開講し、前半は先生からの講義、後半は施設見学がおこなわれました。


最初に教壇に立ったのは吉田久美先生。「アントシアニンを用いた青色着色料の可能性」と題し、講義をおこないました。講義の冒頭、そもそも色とは何でしょうか?と高校生に問いかける吉田先生。さらに色と色素の関係や補色などの解説をしながら、食べる楽しみを向上させる着色料の話へ。着色料は食品添加物の分野に含まれますが、その安全性などについても言及していきました。そしていよいよ本題の「アントシアニン」について。アントシアニンは赤や紫の天然着色料で、pHによって色が変わる特徴を持っています。安全で多彩な色調を発しますが、反面安定性が悪く、コストもかかることが課題です。現在、日本では天然着色料として「クチナシ青」と「スピルリナ青」が認可されており、皆さんがよく知っている氷菓「ガリガリ君」はスピルリナ青を使用していると教えていただきました。またアントシアニンは青いバラ、キク、カーネーションを生み出すことにも活用され、まだまだ課題はあるものの、さまざまな分野への活用が期待される天然着色料であることを伝えていただきました。
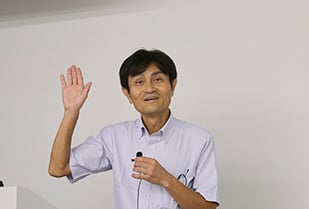

2つめの講義は安藤聡先生による「トマトのおいしさの秘密」。農業・食品産業技術総合研究機構(農研機構)に在籍していた経験を持つ安藤先生は、品種開発のための成分分析や品質評価をおこなってきた経験を元に、トマトのおいしさについて詳しく教えていただきました。日本での野菜の産出額はトマトが第1位であること、トマトの生産地は第3位がここ東海エリアであることなど、トマトに関する基礎的な知識のほか「トマトの摂取量がいちばん多い国はどこ?」といったクイズを出しながら高校生の興味を引いていきます。そして話はトマトの成分に移っていきます。トマトのおいしさは甘味、酸味、旨味のバランスがいいこと。そして旨味はグルタミン酸とグアニル酸という成分による影響が⼤きく、特にグアニル酸は加熱することで増える特徴があり、熱調理によるトマトのおいしさは、グアニル酸がカギを握っていることが知ることができました。
3つめの講義は菅野友美先生による「おいしさを科学しよう!」です。そもそも「おいしさとは何か?」という根源的な問いを高校生に投げかける先生。さらにおいしさを感じる仕組みとして、舌や脳に味がどのように伝達されるのか、それによってどのようなホルモンが分泌されるかなど、専門的な領域も交えてお話していただきました。5味(甘味、塩味、酸味、苦味、旨味)についての詳しい説明のあと、おいしさに大きな影響を与える香りについて、「香りはおいしさの7割を占める」と教えていただきました。それを証明するために配布したアメを食べてもらい、簡単な実験もおこないました。鼻をつまんでアメを食べるときと、鼻をつままないで食べるときの味の変化は明らかで、高校生たちもその意味を実感として捉えていました。その他にもヒット食品は新鮮なテクスチャー(歯ごたえなどの食感)を持っていることなど、おいしさを構成する多くの要素について伝えていただきました。




講義が終わると、1号館の4階と5階にある各施設の紹介に移ります。まずは4階の実習フロアへ移動。ここではテーブルコーディネート室や食品加工実習室など、実習に使用する教室を見学しました。次に5階へ移動し、ここでは食品衛生実験室、食品分析実験室など、実験の授業で使用する教室を紹介しました。見たことのない評価機材や実験装置などを目の当たりにし、先生に質問したりしている姿が印象的でした。ご参加いただいた高校生の皆さんは、講義や施設紹介を通し「愛知淑徳大学食健康科学部 食創造科学科で学ぶ未来」について、より明確なイメージを持てるようになったのではないでしょうか。本学ではこれからも、卒業生や未来の愛知淑徳大学の学生とのつながりを大切にし、彼らの活動や学びをサポートしていきます。












