追究
2024年11月25日
建築・インテリアデザイン専攻 ドットアーキテクツ 展 「POLITICS OF LIVING 生きるための力学」講演会

2024年9月7日(土)長久手キャンパス
建築家の展覧会を学生が企画・設営。
愛知巡回展の会場デザインを担当しました。
創造表現学部 建築・インテリアデザイン専攻で3年生を対象とした授業「デザインワークショップ」では、学生が著名な建築家とコラボレーションし、展覧会場の設計や施工・運営を行っています。今年度は、大阪・北加賀屋を拠点に活動する「ドットアーキテクツ」と連携し、TOTO株式会社が運営する「TOTOギャラリー・間」で開催された展覧会「ドットアーキテクツ 展 POLITICS OF LIVING 生きるための力学」を、学生たちが愛知巡回展として再構成しました。
展覧会は、2024年8月31日(土)~9月15日(日)の間に開催され、9月7日(土)にはドットアーキテクツ代表の家成俊勝さんによる講演会が実施されました。
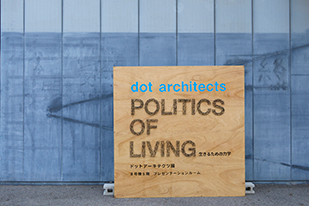
「デザインワークショップ」の授業では、4月に作家研究を始め作品の意図や思想を読み解き、5月からはグループに分かれて設計案を制作します。6月に家成さんへアイデアをプレゼンテーションし、フィードバックを受け、各グループの提案をまとめ、最終プランを決定します。その後、設計班・施工班・グラフィック班に分かれて設営をおこないました。










今回の展覧会タイトルにある「POLITICS OF LIVING」は、「小さな自治空間を生み出す力学」を指します。学生たちは、そのテーマを展示空間にも表現するため、そこにあるものを道具や材料として使用や転用を行い、自ら手を動かして計画を行いました。設営には主に、過去の展覧会で使用された角材や合板などのストック材を再利用し、本来は壁を作るために用いられる長さ3mある木のフレームを片持ちの展示用パネルとして転用したり、ストック材を組み合わせてベンチとして利用したりと展覧会コンセプトに合った会場設営となりました。会場を訪れた他大学の学生や建築家の方、保護者の方々は興味深そうに見学している様子でした。また、家成さんが会場を見学された際には、「ストック材と言わないと分からないね」「すごいものができあがった」と、学生たちのアイデアを褒めていただきました。
















さらに午後からは、家成さんと学生たちの座談会がおこなわれました。今回の会場設営について振り返り、「完成してほっとしました」と話す学生や、コンペについて相談する学生の姿が見られました。今回、ドットアーキテクツが考案した「非電化足踏みろくろ」を本展覧会のオリジナルバージョンとして学生たちも再現し、ろくろを用いてこけしペイント体験を設けました。学生たちがそれぞれ制作したオリジナルのこけしを見比べ、家成さんに「このデザインがいいね」などと褒めていただき、喜ぶ学生の姿も見られました。


その後、家成さんによる講演会が開かれ、今回の展示やこれまでに携わってきた建築についてお話いただきました。始めに学生が施工した会場について触れ、「大変すばらしい展示空間を作ってくださりました。まだご覧になっていない方はぜひ見ていただければ」と伝え、学生が手がけた「足踏みろくろ」についても紹介いただきました。
また、コミュニティ内で物事を決め、進めるという「小さな自治空間」を作り上げた例として、香川県・小豆島の「馬木キャンプ」、大阪・北加賀谷の「千鳥文化」などの建築をご紹介されました。家成さんが手がけた建築物や、それによって生まれた「小さな自治空間」の数々を学生たちは熱心に聞き入っていました。




質疑応答の時間では、「クライアントとの関係の作り方」「『千鳥文化』の現在の運営」などの質問が寄せられました。「建築は完成が最後ではなく、常に実験です。そこで生活する人によって建物が変わります」と家成さんは話し、「だからこそ、自分たちで手を加えることでより深みがでるのだと思います」と伝えていただきました。
「デザインワークショップ」を通して、建築家の考え方、向き合い方を学び、展覧会の施工を成功させた学生たち。これまでの学びの成果が形となり、自信になったことでしょう。本学はこれからも学生たちの体験による学びを後押ししていきます。
学生インタビュー

例年より半数以下の人数で会場設営に取り組むこととなり、少ない人数で最大限の効果を生み出す設計ができるかが一番大変でした。それぞれがリーダーの役割を担い、他のメンバーに指示を出したりしていましたが、メンバーをうまくまとめることができないといったこともあり、苦労もしました。ですが、作業が進行するにつれ、他の班のフォローにまわるなど、人数が少なくても一人ひとりができることを見つけて、メンバー全員で取り組むことができ、最終的にはとてもいい展示空間になったと思います。来場された方に「木の温もりや匂いが感じられてよかった」とコメントをいただき、ストック材など元の素材を使う良さを感じてもらえたのもうれしかったです。今回の授業を通じて、実務の成長はもちろん、リーダーとしての成長もできたと思います。この経験がこれからの挑戦に活きると実感しています。












