追究
2024年12月02日
健康医療科学部 理学療法学専攻 コミュニケーション実習

2024年9月4日(水)長久手キャンパス 13号棟 理学療法学専攻フロア
障がいを持つ方と家族による講演会、交流を通じて
理学療法士としての支援のあり方について考える機会となりました。
本学の健康医療科学部 医療貢献学科 理学療法学専攻は、リハビリテーション専門職としての能力を身につけ、医療機関で役立つだけでなく、地域理学療法でも活躍できる人材の養成に取り組んでいます。
9月2日(月)~5日(木)の4日間に学内および学外の医療福祉施設において「コミュニケーション実習」が行われました。「コミュニケーション実習」は、主に障がいのある子どもや人を対象にコミュニケーション技術とチーム医療における理学療法士の役割を学ぶことを目的としています。学内では基礎知識の習得とコミュニケーション体験、学外での臨床実習、体験発表も含めた実践的体験学習を展開することで障がいに関する理解を深め理学療法士として必要とされる資質を学びます。
9月3日(火)は、多数の障がい当事者やご家族をゲストとして招き学内実習を行いました。2限目は、障がい当事者、ご家族が登壇され、それぞれの立場でご講演いただきました。


始めに社会福祉法人 AJU自立の家の森様が登壇。社会福祉法人 AJU自立の家とは、「重い障がいがあっても、地域で暮らしたい」という思いで、障がいを持つ方が中心となって運営する団体です。森さんは当事者として感じる「分けられる社会環境・分けられる教育」について説明。地域から忘れられること、遊べるおもちゃがなく友達と遊んだ経験がないこと、年齢に応じた経験ができないことなどに触れ、自分で選択・決定ができる「自立生活」ができるようさまざまなことに取り組んでいると紹介されました。「障がいを知ることは、地域生活を知ること、制度と当事者が感じる自立感は違うということをぜひ知ってください」と学生たちにお話いただきました。


家族支援をテーマとした回では、宮部様が障がいを持つ家族と生きることについてご講演されました。双子の妊娠が分かるも、切迫早産で子どもを産み、出産後に双子は脳内出血していることが判明。弟は2歳半でNICUを退院するまで合計15回水頭症の手術を経験します。いざという時に対応できるように、転院先では、夜間の呼吸管理や吸入、吸引、カテーテルの入れ方などを家族が習ったとお話されました。不安な時期を、病院のスタッフをはじめ、病院にいる他の母親や、日本水頭症協会に属する患者やその家族に支えてもらい、「長くて真っ暗なトンネル」を抜けることができたとお話いただき、家族支援について考えさせられる時間となりました。


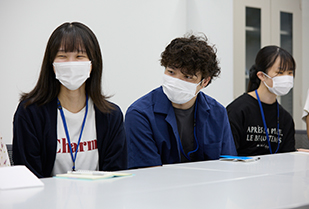

3限目では、コミュニケーション実習として、4名の「障がい当事者」と交流を図りました。始めにお互いに自己紹介をおこない、学生たちは事前に考えてきた質問を投げかけます。趣味や好きなものなどの個人的な質問だけでなく、普段の生活や「やってもらえると嬉しいこと」など支援に関するものもありました。普段、どんな動作練習をしているか、どんなマッサージを行っているかなど、理学療法を学ぶ学生にとって、とても貴重なお話を聞かせていただきました。また、ゲストの方によって、コミュニケーションの取り方も異なるため、顔をしっかり見ながら交流を図る学生たちの姿が見られました。ゲストの方からは、大学で学んでいること、目指していることなどを質問され、互いに理解を深める時間となりました。


障がいを持つ方やその家族との交流を通して、理学療法にまつわる知識だけでなく、コミュニケーションの構築のあり方についても学ぶことができた学生たち。この経験が、今後の実習や学びに活かされることを期待しています。












