追究
2025年01月31日
令和6年度 第2回 文学部講演会「方言は歴史を語る」

2024年11月22日(金)長久手キャンパス 121教室
東北大学・名誉教授 小林隆先生が集めた
全国各地の方言から、日本語の歴史を考察しました。
11月22日(金)、文学部 国文学会が企画・運営する「令和6年度第2回文学部講演会」が開催されました。今回、講演者としてお招きしたのは、東北大学の名誉教授である小林隆先生です。小林先生は方言学を専門として、方言の視点から新たな日本語史の構築をめざす「方言学的日本語史」を提唱し、研究なさっています。今回の講演会では「方言は歴史を語る」と題し、方言の特徴や伝わり方から紐解く日本語の歴史について語っていただきました。


まず最初に触れたのは、文献から見える言葉の歴史です。文献からは上層階層の書き言葉や中央(日本の中心部)の言葉の歴史を知ることができますが、庶民階層の話し言葉や地方を含めた全国の言葉の歴史については情報が少なく、詳しく知ることは困難です。
そこで今回の講演会では、小林先生が用意した資料や実際に全国を尋ねて集めた情報などをもとに方言の特徴から、どのように言葉が広がっていったのかを考察しました。
例えば、方言に残る古語として「かたみに」という言葉が紹介されました。私たちにも馴染みが深い「蛍の光」の歌詞にも「かたみに思う ちよろずの」と歌われているこの言葉は「お互いに」という意味を持ちます。現在の私たちには「かたみに」という古語は馴染みがなくなりましたが、方言には「かたみに」が残っており、「お互いに」という意味で用いられていることが確認できるのです。
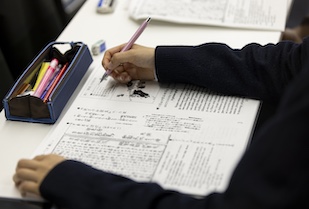

また学生たちが小林先生の研究魂を感じたのは、その行動力です。文献での調査分析にとどまらず、時には地方まで足を伸ばし、情報収集をすると語る小林先生。その研究の成果として紹介されたのが、「〜〜へ行く」という時に使われる格助詞「へ」の方言分布の調査です。
『移動の帰着点』を示す「へ」ですが、宮城県では「東京サ行く」と「サ」になります。遠く離れた宮崎県日南市では「東京サメ行ってくるわ」となり、お隣の大分県湯布院町では「東京サネ行て来でな」と、宮城県とは異なるもののどこか似た音であることに気づきます。
さらに興味深いのが、日南市や湯布院町では、「駅(の方向)にいく」という場合と、「駅に行く」と行き先が明確な場合では格助詞が変化することです。例えば、日南市では、駅の方向にいったという場合は「駅サメ 行たが」となりますが、駅に行ったという場合は「駅ニ 行たど」となり、格助詞が変わることで状況の違いを表しています。
その他、かつて朝の連続テレビ小説で流行した東北方言の感動詞「ジェジェジェ」についても、発祥の地とされる久慈市小袖地区から東北各地にどのように分布しているかを地図上で示したり、「ヤバイ」「アバヨ」「イナイイナイバー」といった今でも使われる言葉が「アワレ」「アッパレ」といったアバ系感動詞から派生していることなどの興味深い説明がありました。
最後に小林先生は、「日本語の歴史は貴族や中央語だけの歴史ではない。庶民や地方語にも視野を広げれば日本語史の厚みや豊かさを増すことにつながる」とお話ししてくださり、「方言は語る。いや語りたがっているように感じる」と、方言に興味を持つことの面白さを伝えてくださいました。
講演後、代表学生が壇上の先生の元へ向かい、感謝の言葉を読み上げると、小林先生は「このように丁寧な感謝の言葉をいただいたことは初めてです」と喜びの表情を見せ、そんな先生のお人柄あふれる様子に会場からは再び大きな拍手が送られました。













