追究
2025年03月07日
【教志会】第10回 教員養成特別講座「教科指導の最前線」

2025年1月29日(水) 長久手キャンパス
教育の第一線で活躍する先生たちをお招きし、
今後求められる教育や各教科の指導法などを学びました。
愛知淑徳大学には、教職課程履修者と教職に従事する卒業生をつなぐコミュニティー「教志会」があります。教志会とは「教員を志す者の会」の略で、学生が企画運営をおこない、現職教員との交流会などを実施しています。
その一環として毎年、「教員養成特別講座」を開催しています。この講座では、講師として愛知県総合教育センターの先生方をお招きし、教科ごとに講義や模擬授業をおこなっていただき、学生たちは授業展開のポイントや今の学校教育について学びます。




本年度は2025年1月29日(水)に実施し、極めて実践的な内容のため、教員をめざす学生たちの貴重な学びの場となっています。また、今回で10回目を迎えました。
以下では、各教科の特別講座の様子をご紹介します。
国語 細澤美沙先生


国語の講座では、高校国語の模擬授業がおこなわれました。題材となったのは古文の和歌である伊勢物語「筒井筒」です。学生たちには原文と現代訳が記されたプリントが配られ、最初に内容を理解しました。その後、「古文の和歌を現代語の手紙に書き換えよう」と題したワークに取り組みました。学生たちは和歌を詠む前後の状況や心情を踏まえ、和歌の詠み手の気持ちになって想像を膨らませました。手紙を書いた後には、学生同士で「相互評価」をおこない、どんな点を評価すればいいのか具体的に学びました。評価後、学生たちは評価を参考に推敲。正しい評価によって学習効果が高まることを実感しました。
英語 山田和幹先生


ご登壇いただいた山田先生は、「教科指導力を高める『指導のアイデア・指導法の工夫』」と題して、最初に横浜国立大学による調査研究書をもとに、今の中学校の英語教育の実態や課題についてお話しされました。学生たちは、今の英語教育について、英語で話すこと・書くことの力の育成が課題となっていることを知り、今後、言語活動を活発化させるための取り組みについて考えました。そして、山田先生から言語活動の視点から授業づくりのポイントを学び、学生たちは今後大きく変わる英語教育のあり方に真剣に耳を傾けていました。
社会 伊藤直宏先生


伊藤先生は最初に2種類の白米を学生に配り、食べ比べをおこないました。この2種類は国産米とアメリカ産米であり、味もさることながら、価格が大きく異なります。伊藤先生は「どうして価格が違うの?」「どうしてアメリカ産米は入ってこないの?」「アメリカ産米が入ってきてもいいと思いますか?」と学生たちに問い、みんなでディスカッションしました。その上で、学生たちに社会科という教科は何を学ぶのかを伝えました。伊藤先生は、社会は人が形成しているとして「社会科は人から学ぶ」と語られ、社会科は常に「人」を意識できる授業づくりをめざしてくださいとアドバイス。具体的な授業づくりのコツについて教えてくださいました。
保健体育 渡辺美穂先生


サブアリーナにておこなわれた中学体育の模擬授業(実技)では、室内で楽しめるタグラグビーをおこない、みんなで汗をかきました。タグラグビーは腰につけたタグを取られないように動きながら、相手のタグを抜き取るゲーム。小学生から大人まで楽しめるゲームとして学校現場でも多く取り入れられています。後半は、体育教員の勤務スケジュールや魅力を紹介。渡辺先生は保健体育の楽しさとは「する、見る、支える、知る」の4つの観点があると示し、運動能力の差に関係なく、生涯にわたって心身の健康を保持増進し、豊かなスポーツライフを実現する資質・能力を高めてほしいと話してくださいました。
幼稚園 加藤綾子先生


前半では「幼児の描画活動をどう支えるか」というテーマで講義がおこなわれました。協同性や自立心、思考力の芽生えなど、幼児期で育ってほしい10の姿を紹介し、幼児の描画ではどの力が育まれるのか、子どもの絵の発達段階を見ながら、学生たちと一緒に考察しました。後半はワークショップ形式で「雨の日の楽しい室内遊び」として、新聞紙を使った遊びを考えました。この時、10の姿のうち、どんな育ちが期待できるかを念頭において考えるのがポイントとのアドバイスがありました。保育者や幼児の目線になって遊びを考えたことで、子どもへの接し方を知る機会にもなり、現場でいきる学びとなりました。
小学校 杉山寛仁先生


杉山先生は「学習意欲を高める!!楽しい授業づくり」と題して、小学2年生の生活科の模擬授業をおこないました。授業内容は「めざせ!!紙ひこうき博士」。杉山先生は、紙ひこうきを遠くまで飛ばすにはどうしたらいいかな?と問いかけ、学生たちは自分が作った紙ひこうきを飛ばしながら、「友だちと比べてどう思ったか」「遠くまで飛ばすにはどうしたらいいか」などを考えました。後半は、少子化やグローバル化など教育を取り巻く社会の構造変化を学びました。杉山先生は、これからは「子どもが自ら学びとる授業」が求められると話し、小学校教員をめざす学生たちに「子どもと過ごす楽しさや子どもの成長を感じる幸せを大切にして、自分のよさを生かして、まわりに頼りながら楽しくし仕事をしてください」とエールを送ってくださいました。
特別支援 西島謙一先生
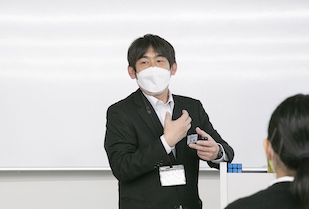

西島先生の講義では、「特別な支援を必要とする子どもの理解と支援」について、特別支援教育のめざすところは「卒業後の楽しみ、やりがいをみつけられるようにすること」だと示しました。その上で、各教科指導では、授業の中で日常生活や遊び、コミュニケーションを含む自立活動などを併せ持って指導することの重要性を伝えました。中でも自立活動について深くお話しされ、個性が異なる子どもたちに対し、どのような点に配慮しながら指導すべきかさまざまな事例を紹介。また特別支援クラスや施設で活用されている補助具やICTの活用事例なども紹介し、最後には「特別支援教育は、子ども一人ひとりの教育的ニーズに応じたオーダーメイドの教育」と話し、そのやりがいを学生たちに伝えてくださいました。












