追究
2025年03月19日
食創造科学科 基礎演習 和菓子商品企画のお茶会

2025年1月27日(月)国際交流会館1階茶室
浅井屋製菓舗と協働で開発した和菓子「祝ASU50周年」を
国際交流会館の茶室で抹茶と共にふるまいました。
本学の食健康科学部 食創造科学科では、食品学、調理学、健康学、栄養学、食文化、食創生の6つの領域から、食に関する幅広い知識を修得し、新たな食の創造に貢献できる人材の育成をめざしています。必修科目となる食創造科学基礎演習の加藤友紀ゼミでは、商品開発の一連の流れについて基本的なことを学びました。コンセプトシートを作成し、ターゲット、キャッチコピー、販売価格、商品のベネフィットを考えた商品を提案し、試作や栄養価計算まで行いました。その一環として、長久手市の和菓子店「浅井屋製菓舗」様を訪問し、商品開発について和菓子職人さんからお話を伺い、実際に和菓子づくりを体験。そして今回は、浅井屋製菓舗と協働し、本学の開学50周年を記念する和菓子「祝ASU50周年」を開発。2025年1月27日(月)、国際交流会館1階の茶室にて、完成した和菓子とお抹茶をふるまうお茶会を開催しました。


和菓子「祝ASU50周年」は、愛知淑徳大学の3つの色を取り入れ、形状は新1号棟をイメージ。大学生にも和菓子に興味を持ってもらえるよう、クランベリー餡を使用しています。また、抹茶は西尾市にある赤堀製茶場の有機栽培の茶葉による「波」と「天楽」の2種類いずれかを訪れた方に選んでいただき、提供。「波」は、苦みが少なめで、抹茶が苦手な方でもすっきりと飲みやすい味わい、「天楽」は上品な苦味が感じられ、抹茶好きな方におすすめの一品です。
前期に開催された学術講演会では、茶道裏千家正教授の神谷宗舎長(ソウチョウ)先生より、お茶の点て方や、お茶やお菓子のいただき方について実践指導を受けた学生たち。今回のお茶会では、学生たちがお抹茶を点て、和菓子と共に訪れた方にふるまい、和菓子やお抹茶についての説明をすることで、改めて和の食文化を学ぶ機会にもなりました。
■2024年度 第1回 食創造科学科 学術講演会 「茶事に見られる茶と食の関係について」>



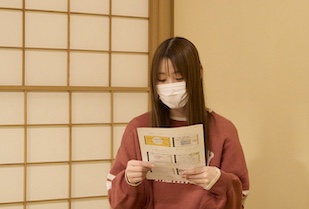
また、今回の和菓子の商品開発のタイミングにおいては、和菓子に限らず、学生一人ひとりが1年間の学びの締めくくりとして、商品開発をプレゼンテーションしました。食創造科学科1年生の学生にとっては、初めてとなる商品開発のプレゼンテーション。大平彩菜さんは「想像していたよりも多くの視点で物事を考えなくてはいけないことが難しかった。また、考案した商品を実際につくってみたところ、自分が思い描いていた形状で提供すると形が崩れてしまうことがわかり、試行錯誤しました」と話し、実際に経験したからこそ得られた学びは大きかったようです。また、野菜を使ったお菓子を考案した水谷愛彩さんは、「新しいものをつくろうと考えていたのですが、調べてみると、世の中に既に存在するものが多く、新規性を出すのに苦労しました」と、考えれば考えるほどに商品開発の難しさを痛感したことを明かします。

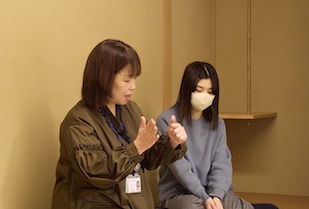
最後に加藤友紀先生より、「今回は1人で商品開発に取り組みましたが、今後複数の人数で取り組む際には、いろんな意見を説得しなければいけない大変さも加わります。また、今回は全体の流れをまず考えてみましたが、コンセプトや栄養価など、さまざまな枝葉をこれから追求していってほしいと思います」との言葉で会が締めくくられました。実践的な学びを通し、商品開発の魅力だけでなく、大変さも実感した学生たち。それにより、2年生からの学びをさらに深めていけることでしょう。












