追究
2025年07月11日
愛知淑徳大学 開学50周年記念講演会 「国際結婚から考えるダイバーシティ -フィリピン人の妻と家庭を築き、気が付いたこと」
2025年度 学園創立120周年・大学開学50周年記念行事 展示会・講演会・発表会

2025年6月6日(金) 星が丘キャンパス 講堂
在日フィリピン人女性との出会いから結婚、子育てを通じ、
学生たちに「共に生きること」の本質を語っていただきました。
2025年度、愛知淑徳学園は創立120周年、愛知淑徳大学は開学50周年を迎えました。その節目の年を記念して、2025年6月6日(金)、ダイバーシティ共生センター主催の講演会が開催されました。
お招きしたのは、『フィリピンパブ嬢の社会学』『フィリピンパブ嬢の経済学』の著者で、在日フィリピン人を中心に取材や執筆、講演活動を行っている中島弘象さんです。『フィリピンパブ嬢の社会学』は、中島さん自身の経験を社会学的な視点から紐解いた作品で、大学院生としてフィールド調査のために出向いた先のフィリピンパブにおいて、研究対象だったフィリピンパブ嬢のミカさんが、いつの日にか恋愛対象に変わっていき、その過程で目の当たりにしたそこで働く女性たちを取り巻く厳しい実態を描いており、2024年に映画化されました。
講演では、書籍で描かれている通り、フィリピン人女性、具体的にはフィリピンパブ嬢と国際結婚した中島さんが、交際・結婚・子育てをする中で感じたダイバーシティの難しさや大切さについてお話しいただきました。
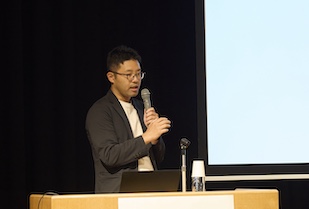

講演の冒頭では、日本にフィリピン人が増加した1980年代の日本の実情が説明されました。当時、歌手やダンサーとして活躍できる「興行」ビザが発行され、日本全国の繁華街にフィリピンパブが誕生。「興行」ビザを取得した多くのフィリピン人女性が日本を訪れ、その数は毎年数千人にものぼったそうです。ところが、ビザを取得するのは非常に難しく、歌手やダンサーである証明書を取得するためには、フィリピンの養成所に泊まり込んで練習し、資格試験を受けなければならなかったそうです。試験の合格率は10分の1程度。かろうじて資格を取得できたとしても、プロモーターのオーディションに選ばれなければ日本に行くことはできなかったということです。100人に1人という難関オーディションを突破し、念願の日本へ行くことができても、フィリピンパブでの仕事の多くは、お客様である男性のお相手をする水商売のような仕事ばかりでした。やがて「興行」ビザが人身売買の温床になっているのではないかと言われるようになり、フィリピン人女性がセクハラや性暴力、殺人などの事件の被害に遭うケースも増えたことから、2005年に「興行」ビザの発行に規制がかかり、フィリピンパブは数を減らしていきました。


中島さんが初めてフィリピンパブを訪れたのは大学時代のことです。全盛期は過ぎていたものの、名古屋の繁華街にはまだ100軒程度のフィリピンパブがあり、若いフィリピン人女性がたくさん働いていました。「興行」ビザは規制がかかっているはずなのに、なぜこんなに多くのフィリピン人女性が日本にいるのか?と疑問に感じた中島さんは、大学に戻り論文を調べてみると、2005年以降はフィリピンパブについて取り上げた論文や資料がないことに気づき、大学院に進学してフィリピンパブについて研究することにしました。それからフィリピン人女性にインタビューするために、フィリピンパブに週1〜2回通ううちに、中島さんは彼女たちの裏にある闇を知りました。
それは、「興行」ビザが規制されたことにより日本への渡航の道が塞がれてしまったため、日本に来るために日本人男性と偽装結婚をしていること。日本での休日は月2日だけであること。働く場所、住む場所、一緒に住む人もすべてマネージャーと呼ばれるブローカーに決められ、外出する自由がないこと。毎日働いても月6万円しかもらえないこと。契約も口約束のようなものばかりで、時には400〜500万円で女性が売られていくこともあるなど、彼女たちを取り巻く現実を知り、「映画やドラマのような世界が本当にあるんだ」と衝撃を受けたと語られました。


のちに中島さんはフィリピンパブで出会ったミカさんと交際。「こんなに過酷なのに、なぜ日本に来たの?」と聞くと、ミカさんは「あなたは本当の貧乏を知らない」と答えました。フィリピンでの貧しい生活を乗り越えるために来日し、フィリピンパブ嬢としての生活は厳しいが、フィリピンにいた頃よりもずっといいと語る姿に、中島さんは同じ年齢の日本人女性とは大きく異なる現実に震撼したそうです。
しかし、そんな暮らしであるにもかかわらず、「日本に連れてきてくれて感謝している」とマネージャーを恩人のように思うフィリピン人女性は少なくなかったそうです。
数年後、中島さんはマネージャーとの契約が終わったミカさんと結婚。しかし、結婚後の生活もミカさんにとっては大変なことばかりだったと話します。 漢字の読み書きができないミカさんにとって、病院や役所は一人で行くことができず、また小学校に上がった子どもたちがもらってくる学校からの手紙も理解できませんでした。生活上のほとんどを夫の中島さんに頼らざるを得ない状況でしたが、それでもミカさんは「日本の行政は外国人にも丁寧に向き合ってくれる」「ママ友たちはわからないことは手伝うよと寄り添ってくれる」と言い、日本での子育ての苦労を感じさせないくらい、前向きに楽しそうに暮らしているのだそうです。


こうしたミカさんの人生、また育児への関わりなど、国際結婚家庭での家族の営みを通して多くのことを学び、書籍にして伝え続けている中島さん。現代社会の様々なところで多様性が拡がり、「多文化共生」という言葉を耳にする機会が増えています。私たちは「相手の文化を知らないといけない」「相手を受け入れないといけない」と思いがちですが、中島さんは「外国人を受け入れよう支援しようというのではなく、共に生き、助け合い、学び合うという姿勢が大切だと思います」と語りかけていました。講演の最後に、学生たちに向けて「愛知淑徳大学には『違いを共に生きる』という理念があると聞きました。違いを認め合うというのは、自分のことも知り、相手を知って、同じところを探す作業だと思います。違いを見つけて、認めて、共通点を探してほしいと思います」とメッセージを送ってくださいました。












