追究
2025年09月30日
ビジネス学部 専門教育科目「私のシゴト学」第2回~第5回
2025年度 ビジネス学部 展示会・講演会・発表会 進路・就職

2025年4月23日(水)~6月4日(水) 星が丘キャンパス55A教室
さまざまな業界のプロフェッショナルから、
就職活動における心構えや
仕事に取り組む意義について学びました。
ビジネス学部ではビジネスに関する専門知識や実践的なスキルを身につける科目が多数用意されています。その中でも特徴的なプログラムが3年次に開講される「私のシゴト学」です。さまざまな業界で活躍するプロフェッショナルからその体験談を聴くことで、働くとは何か、仕事に取り組む意義などを学ぶのが目的です。また講義を通じて、就職活動に臨む学生たちの糧にもなると考えています。
2025年度「私のシゴト学」は4月16日(水)から6月4日(水)まで毎週開催され、全8回で構成されています。第1回目はガイダンスのため割愛し、今回は第2回~第5回の様子をご紹介します。
【第2回】4月23日
本学キャリアセンター アドバイザー 山本貴代様/
株式会社三菱UFJ銀行 北條真子様
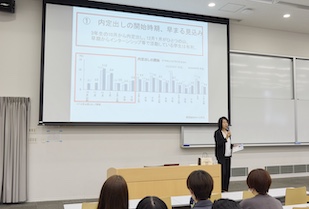

第2回目は前半と後半の2部制になっており、前半は本学のキャリアセンターの山本アドバイザーが登壇しました。山本様は長年、本学の就職サポートのエキスパートとして学生を支え続けています。そんな山本様が最初に強調したのは、2年生の12月から就職支援ガイダンスはスタート、3年生の1月から就職活動の本番であること。多くの学生が「そんなに早く!?」と感じたに違いありません。しかし、それが現在の就職活動の実情であり、気持ちをしっかりと就職活動モードに切り替えてほしいと主張されました。
その他にも夏と秋冬のインターンシップに参加すると採用に関する情報等が得られることや、昨今はSPIが重要視されてていることから数学の学力がポイントになることなど、有益な情報を教えていただきました。また、インターンシップでは業務を体験するだけでなく、会社全体を広い視野で見て、その企業の良いところ等をしっかりと観察し、自分が働き続けることができる会社かどうかをしっかりと見極めることも大切だとアドバイスしていただきました。


後半は本学のビジネス学部の卒業生で現在は三菱UFJ銀行に勤務する北條真子様に、ご自身の過去を振り返りながら学生時代の経験や就職活動について、お話しいただきました。学生時代は某コーヒーチェーンでアルバイトをし、そこで接客の楽しさやチームで働く難しさを学ばれたそうです。インターンシップでは名古屋に本拠地を置く総合IT企業で1年半の間、営業やテレアポを経験し、営業の楽しさや難しさを実感されました。そして大学2年生の夏から就職活動を開始。自己分析をはじめ、キャリアセンターを積極的に活用し、30名のOB/OG訪問を行うなど、とにかく“動くこと”をテーマに活動されました。
北條様は、業界選びでこだわった部分があり、そのこだわりを3つ挙げていただきました。1つめは人間力で勝負したいため、無形の商材を扱う業界であること。2つめは話すことが好きなので、人と密に関わる業界であること。3つめは自分の成長をお客様に還元できる仕事であること。その3つを備えた業界が“金融”であり、三菱UFJ銀行を選びました。現在、北條様はスタートアップ企業約80社と学校法人を担当し、お客様の成長のための支援活動をおこなっています。この仕事には学生時代のアルバイトやインターンシップなどの経験が生かされていると伝えました。
最後に北條様は学生たちに向けて、筆記試験対策をしっかりとおこなうこと、早めに動くこと、自己分析をしっかりすること、そして面接は場数を踏むことの4つをアドバイス。就職活動は自分が行動した分だけ必ず結果が付いてくるもの。人生に一度しかない新卒ブランドを無駄にしないよう全力を尽くしてくださいとエールを送りました。
【第3回】4月30日
セレンディップ・ホールディングス株式会社取締役CIO 髙村徳康様
第3回のこの日は名古屋市に本社を置く「セレンディップ・ホールディングス株式会社」で取締役CIO(チーフ・インベストメント・オフィサー)を務める髙村徳康様にご登壇いただきました。セレンディップ・ホールディングス株式会社は中小企業の成長を支援するパイオニアとして、経営の近代化や事業承継など、さまざまなサービスを提案している企業です。髙村様は現在、CIOとして事業承継の支援やM&A業務などに従事されています。髙村様の講義は学生時代から現在にかけて起こったさまざまな出来事から、ご自身がどのような気付きを得たのかを分かりやすくまとめてお話しいただきました。


髙村様は公認会計士に憧れを抱き、大学は経済学部へ進学。卒業後は証券会社に入社し、公認会計士の勉強を続け、29歳で念願叶って資格試験に合格されました。大手監査法人に転職されましたが、実際の業務が自身の興味に沿わず、「憧れだけでは仕事は続かないこと」に気付かれました。その後、ベンチャー支援に興味を持ち、支援機関を立ち上げ初代責任者に就任されました。さまざまな企業の経営をサポートし、その仕事が認められ、経済産業大臣賞やニュービジネス協議会会長賞を受賞されました。このとき髙村様は初めて心から仕事が楽しいと実感し、仕事は「楽しいことしか続かない」との気付きを得られました。
その後、セレンディップ・ホールディングスを起業しましたが、最初の7年間は経営が軌道に乗らなかったと振り返ります。そんな中、赤字続きのベーカリー事業の再生に取り組み、開発した新商品がメディアでも注目され、東証マザーズ市場(現、東証グロース市場)に上場を果たすことができました。ここでの気付きは「ピンチはチャンスに変えられる」ということ。自分が楽しいと思うことを続け、家族や仲間の支えと創意工夫の精神があったからこそ、この結果を生み出せたのではないかと自己分析されました。


最後に髙村様は以前の日本企業と現在世界的に活躍している企業を比較し、今後は問題解決ができる“Skill”よりも、イノベーションや共感を生み出す“Creative”のほうが重要であると強調されました。そして「人生で失敗しないために」とし、3つの教訓を伝えていただきました。1つめは、自分の夢を決め、好奇心を持つこと。2つめは、分からないことがあれば質問をして挑戦してみること。3つめは、それによって創意工夫する力を付けること。これまでさまざま成功や失敗を経験してきた髙村様だからこそ伝えることができるメッセージで、この日の「私のシゴト学」を締めくくられました。
【第4回】5月7日
愛知海運株式会社 国際事業部 外航輸送課 川原大空様
第4回はビジネス学部の卒業生であり、愛知海運株式会社に勤務する川原様にご登壇いただきました。講義のテーマは「海運業界で働くということ」。「学生にあまり知られていない業界だからこそ、この機会に仕事内容を知ってほしい」との想いを込めて、お話しいただきました。


川原様は、2021年に本学を卒業してから愛知海運株式会社に入社し、海上コンテナを輸送するための配車業務や在来船の配船業務を経験されました。
海運事業とは、船舶を用いて物資を国内外に輸出入することを指し、現在の海上輸送はコンテナ船が主力であることを教えていただきました。コンテナは物資を運ぶための規格化された「箱」であり、効率的に輸送するために欠かせないもので、用途によってさまざまな種類があります。また、空輸との違いについても言及。海上輸送は一度に大量のコンテナを運ぶことができ、コストも抑えることができ、環境にやさしいことを強調されました。
続いて、愛知海運株式会社の紹介をしていただきました。1943年に設立した歴史ある企業であり、本学の卒業生が13名在籍しています。地域に根差した企業を目指し、1日数千トンの物資を扱っていること、環境への配慮に積極的であることなども紹介。併せて川原様の仕事内容や1日のスケジュールについても説明されました。


学生時代に経験してよかったことについては、簿記の勉強や海外インターンシップ、ダンスサークルではチームをひとつにまとめてイベントを成功に導いた経験が仕事でも生かされているとお話ししていただきました。総じて学生時代に身に着いたものとして「計画力、コミュニケーション力、積極性」の3点であることを結論付けられました。就職活動については、なるべく早く動くことを第一に掲げられ、自己分析と業界研究をするとともに、その業界で何をしたいのかをしっかり考え、面接では自分の言葉で話すことが大切だと学生たちに語りかけられました。
最後に川原様にとって働くとは「自分らしさを生かし、誰かの役に立つことである」とし「失敗してもいいので、視野を広げ、多くの人と出会うことが大切です」と学生たちにアドバイスしていただきました。
【第5回】5月14日
オカタ産業株式会社 代表取締役社長 岡田哲士様
第5回は豊田市に本社を置く「オカタ産業株式会社」の代表取締役社長である岡田哲士様にご登壇いただきました。オカタ産業は自動車部品を運搬する際に使用するパレットやモジュール、移載機、部品棚などを一貫生産している会社です。その会社を指揮する岡田様の講義は「『インベスターZ』というマンガを知っていますか?」という質問から始まりました。『インベスターZ』はお金や投資について書かれた作品で、作中に「働くなら大手企業か? ベンチャーか?」 という内容が出てきます。講義では大手とベンチャーの両方で勤務された経験から岡田様が考えるそれぞれの違いについてお話しいただきました。


岡田様は高校まで名古屋で過ごし、大学は東京へ進学されました。そして26歳のときにベンチャー企業に就職し、33歳で大手企業に出向した経験をお持ちです。
ベンチャー企業では、経営者の判断や考え方を目の当たりにできたことが学びだったとおっしゃいます。もともと管理部門の仕事に興味があった岡田様でしたが、ベンチャー企業では営業職や人事職に就くことに。しかしこの経験によってさまざまなスキルを身につけることができたと話されます。「人生、何が幸いするか分からない」とし、「自分の意にそぐわないことでも、置かれた場所で一生懸命取り組めば、その経験がいつか役に立つときが来ます」と伝えてくださいました。


大手企業では、初めて取り組む仕事で分からないことが多い中、積極的に動いてその道のプロフェッショナルを探し出し、ヒアリングしながら仕事の進め方を体得していきました。仕事をスムーズかつスピーディーに進めるためには、自分が動くだけでなく、手順をしっかりと見極めることが重要であることも学ばれたそうです。
最後に、ベンチャー企業と大手企業の特色を岡田様の経験からまとめてくださいました。ベンチャー企業は自分でやることが多い分、守備範囲も広く、多くの経験を積むことが出来る良さがあり、大手企業では範囲は狭いものの、より深く業務に向き合えるとし、手順を踏んだ仕事の進め方も学ぶことができると述べられました。学生たちにとって、自分のあるべき姿を実現するためにはベンチャー企業なのか、大手企業なのかを考えるきっかけになりました。












