追究
2025年09月01日
建築学部 「Yura Yoshinori’s Talk Event:主体的活動を通した保育について」

2025年6月17日(火)長久手キャンパス8号棟4階プレゼンテーションルーム
『桜井こども園』を運営する由良様から
保育設計のヒントをいただきました。
愛知淑徳大学の建築学部では、まちづくり、建築、住居、インテリアまで、幅広いスケールの空間・環境について実践的に学んでいます。この日は、間宮ゼミの間宮晨一千先生が設計を手がけた『社会福祉法人碧明会 桜井こども園』理事長兼園長の由良宜寛様をお招きし、トークイベントを開催しました。


保育空間を考えるうえでの事前知識として、由良様は会場に集まった学生たちに保育の現状や、こども基本法について解説。「親だけでなく、国や地域全体で子どもを育む社会をつくっていく流れに変わってきています」と語り、それを踏まえた園の取り組みを紹介していただきました。
『桜井こども園』では、「心のふるさとを子どもたちに」という教育方針のもと、遊びや体験を通して、豊かな自然、温かな言葉、人との関わりの大切さを伝えています。
園の様子を撮影した写真には、同じ部屋で給食を食べている子、遊んでいる子、昼寝の準備をしている子の姿も。「幼児期に大切な育ちは、主体性、意欲、協調性、やり抜く力などの非認知能力です。一番の学びは遊びなので、当園では遊びのきりがついた子から食事へ。食べ終わったら次の遊びへ行き、昼寝がしたい子は準備をします」と由良様は話されます。
一人ひとりを尊重し、成長を見守る保育をモットーに、子ども自身が選択して決める環境をつくっているそうです。自由時間には、園庭で年上や年下の子と一緒に遊ぶことも可能で、自然を身近に感じながら、子どもたち自身が遊びを見つけて楽しめる場になっています。

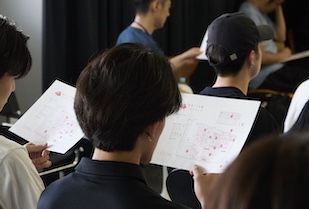
子どもの個性を伸ばしつつ、地域の人なども含めた“私たち”という感覚も学べるように、活動を広げているという由良様。和太鼓や茶道を通して、社会と関わる機会を作っています。保護者や地域の方の発案で、花育、パン作り、カフェなども始めました。職員だけではできることに限りがあるため、企画や段取りはすべてお任せし、場所を提供しています。園を地域交流の場として開放することで、園児、保護者、職員、地域住民みんながワクワクするサイクルを生み出しています。「子どもが自分でやりたいことを見つけ、主体的に行動して学んでいけるよう、いろいろなアプローチで保育を考え、試行錯誤している最中です。建築を専攻するみなさんも多様な考えに寄り添っていただけたら」と伝えました。




設計を担当した間宮先生は、「みなさんに知ってほしいのは、共生することの価値です。園を運営する人の思想を踏まえ、設計の中でどうすればいいか考えてみてください」と語り、配置計画や動線、エントランスの機能性、低年齢児への配慮をスライドを用いながら説明。卒業制作で『桜井こども園』のロゴを担当した卒業生の籔井様も登壇し、どのようなプロセスで進めていったのかをお話していただきました。
終盤では、「年齢の違う子の教室はしっかり仕切った方がいいのか、ゆるやかに区切って交流できるようにした方がいいのか知りたい」、「保育士さんの配置の工夫は?」など、学生たちが積極的に質問。教育方針から導く保育園設計のヒントを知る機会となりました。












