追究
2025年09月19日
ビジネス学部 グループワークⅡ成果報告会

2025年7月24日(木)星が丘キャンパス4号館
現在の⽇本社会における課題解決のアイデアを考え、
プレゼンテーションしました。
ビジネス学部ではコミュニケーション力や行動力などアクティブな学びを通して、社会に求められるビジネスパーソンを育てることを目指しています。そのような多様な力を身に付けるのに役立つのが、1年次に少人数ゼミで開講される「グループワークⅠ・Ⅱ」です。グループワークⅠではビジネススキルを学び、グループワークⅡでは、与えられた課題をチームでリサーチし、アイデアを出し合ってプレゼンテーションをおこないます。
7月24日(木)には、集大成となる「グループワークⅡ成果報告会」があり、9つの課題に対し、各8チームがプレゼンテーション。全チームの発表の後には、投票により、最も優秀なアイデアが選出されました。


発表の様子
41B/コメ輸入自由化を行うべきか

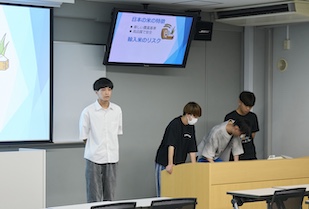
消費者にとって、購入するお米の品種や価格の選択肢が増えることから、「コメ輸入自由化」に賛成する案が発表されました。輸入自由化の一方で、米農家が減少してしまうという懸念も。そのため、水田のサブスク制を取り入れて収入が約束されるようにするというアイデア、米粉商品専門店を開設して日本米の売上を後押しするというアイデアなど幅広い視点から提案をし、このテーマを担当した教員からは「独創的でおもしろいアイデア」との講評がありました。
41C/若者に刺さる新しいブックカフェを提案しなさい
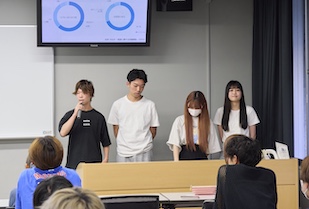

大学生の読書状況をリサーチしたところ読書離れが進んでいることがわかり、その理由として「ゲームのほうが楽しい」「友人と話したり遊んだりするほうが楽しい」という意見があったことから、ゲーム要素があって楽しめる「謎解きブックカフェ」を提案。まず、本のジャンルを選択して挑戦状をもらい、軽食・ドリンクを購入し、挑戦状から1冊の本に辿り着き、その本を読むことで謎解きができるという仕組みです。謎解き要素がありながらも「本を読むことの楽しさを伝える」ことに重きをおいたアイデアには、聴講した学生たちも興味津々の様子でした。
41F/日本の農産物の輸出を増やすために、どのようなプロモーションが必要だろうか

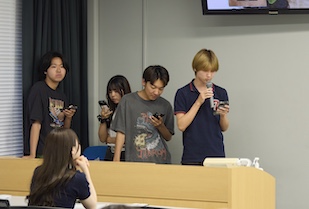
健康にも良いうえ、とぎ汁が掃除にも活用できるなど、さまざまな魅力にあふれる米の可能性に着目。また、海外で流通している米の種類や、海外における米の流通量をリサーチし、日本よりも海外のほうが米の流通量が多いことも米を題材に選ぶ裏付けとしました。しかし、米をそのまま輸出しても、日本米よりリーズナブルな海外のお米と競争するのは難しいと考えた学生たち。そこで、和牛など海外で喜ばれる日本食材とセットにして輸出するのはどうか?というプロモーション案が発表されました。
42A/大学に新たに導入するとしたら、どのようなサブスクサービスが学生に喜ばれるか
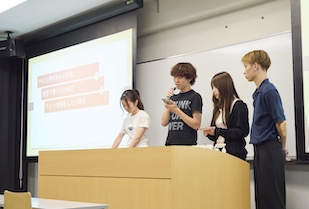

提案されたのは、「月謝制で自分のニーズに合ったパソコンをレンタルできるサブスク」。パソコンは大学在学中4年間使うものですが、持ち運ぶのに重たいうえ、授業によって必要なスペックが異なり、学生にとって日常にも金銭的にも負荷があります。そこで、収納施設を大学内に設け、サブスクでその都度必要なスペックのパソコンが使用できれば、学生にとってメリットが大きいということも説得材料に。さまざまな角度から合理的に考えられた提案は、実現性の高さを感じさせました。
42B/星ヶ丘駅周辺で、大学生として成長できる施設を作るとしたら、
どこにどのような施設を作るか
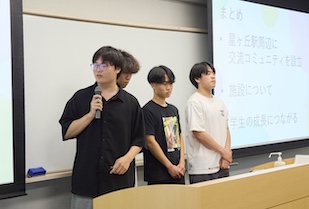

正社員と非正社員では、正社員のほうが人手不足の割合が高いというデータを提示し、企業が人手不足に陥っていることを数値化。その一方で、学生は将来(仕事)への不安を抱いているというアンケートデータを示しながら、双方の課題を解決するために学生が提案したのが、企業と学生をマッチングさせる施設です。交流の場にもなることで、直接的な人材マッチングにつながらなくても、企業は学生の考えを聞くことができたり、学生は社会人と会話することで将来への視野を広げられたりと、双方にメリットがあることを訴えました。
42C/日本の人口減少と少子高齢化が止まらない。
なぜこのような現象が起こったのか、この現象はどのような問題を引き起こすか、
そして最後にその解決策を提案しなさい

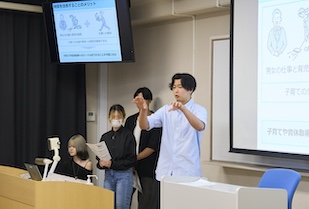
高齢化の原因について、医療技術の向上により平均寿命がのびていることを示した学生たち。人口減少や少子高齢化の解決策として、新婚への住宅費や引っ越し代の補助、残業の削減でワークライフバランスを整えて夫婦ともに子育てできる環境づくりや、三世代世帯の家庭に補助金を出すことで、新米ママの育児への不安が解消できることを提案。結婚や出産のハードルが下がることで、出生率が上がり、若い世代が増えるにともない社会保険制度が整い、全世代が安心して暮らせる社会になると述べました。
42D/若者が「地方で暮らしたい」と思える社会にするにはどんな仕組みが必要か


若者が地方で暮らすことでネックになる「生活利便性」に着目し、車にまつわる支援対策案を発表。1つめは「車両購入割引」、2つめは「ガソリン価格割引」です。ガソリンスタンドでは免許証をかざせば割引サービスが受けられるなど、車を所有し、活用していくことのハードルを下げることで地方での生活利便性が上がるという提案です。担当した教員からは「車を運転したくないという人もいるかもしれないので、そういう人も掬い上げられるような案があるとよいですね」との指摘もあり、さらに考えを広げるきっかけにもなりました。
42E/MJGA(Make Japan Great Again:強い日本をもう一度!)。
実現のために政府がなすべき方策を考えなさい


学生からは「英語教育から強い日本へ」というテーマで、英語教育に焦点を当てた提案が発表されました。国際社会において必要な英語であるが、日本の英語力は他国に比べて低水準だという課題が露見。「英語教育推進政策」として、国を挙げて、幼児から小学生、中学生に至るまで英語教育を取り入れていくべきだという提案です。年齢に合わせて、楽しみながら取り組めたり、幼少期から習慣化できるようなプログラムも具体的に考案しました。
42F/空き家を活用したポップアップショップ運営


名古屋市西区の円頓寺商店街を舞台に、ポップアップショップのアイデアを提案。「愛で商店街を救う」というテーマで、カップルをターゲットに、2人で楽しんで訪れることができ、より愛が深まるようなショップを3つ提案しました。1つめは「商品発掘ストア」。中が見えないカプセルを2人で割り、何が出るかはお楽しみ、というものです。2つめは真っ暗で見えない空間にドキドキ感が高まる「視覚遮断ストア」、3つめは指令にもとづいて気持ちを伝え、恋みくじが楽しめる「恋愛商店」です。グループ全員で「愛!」と発声を揃え、プレゼンテーションの仕方も印象に残るものでした。












