追究
2025年10月14日
ビジネス学部 中小企業を学ぶ③

7月4日(金)18日(金)24日(金) 星が丘キャンパス 55C教室
中小企業のあり方や戦略、働き方について考える有意義な時間となりました。
ビジネス学部では、専門知識の習得にとどまらず、実際の現場で活かせる実践的なスキルを磨くための多様な授業を展開。その一つである「中小企業を学ぶ」では、実際に中小企業で活躍する経営者や従業員の方々を講師としてお招きし、企業のリアルな姿や学生一人ひとりが“自分にとって働くとは何か”を考える貴重な機会となっています。最終回は、7月に開催された講義の様子を紹介します。
7月4日(金)
中小企業経営者と中小企業政策~金融問題から政策理念の形成、地域政策へ/
愛知中小企業家同友会 事務局次長 池内秀樹様
7月4日(金)には、愛知中小企業家同友会の事務局次長・池内秀樹様が登壇し、「中小企業経営者と中小企業政策~金融問題から政策理念の形成、地域政策へ」と題して、1999年の中小企業基本法改正以降の中小企業のあり方や社会の動きについてご講義いただきました。自己紹介と愛知中小企業家同友会の事務局の仕事を紹介した後、「今回の講義は、5月2日に本カリキュラムの担当である浅井先生の講義『中小企業基本法の変遷(1963年と1999年改正法の比較)』の振り返りとして、普段から中小企業に関わる立場としてお話しします」と学生に伝え、講義が始まりました。


講義内容は非常に深く、法や政策といった一聞しただけではわかりづらい内容を学生たちにわかりやすく解説してくださいました。例えば、講義の本題に入る前に、4月から5月上旬に行われた浅井先生の講義を3つの要点にまとめて紹介。中小企業基本法は1963年と1999年に制定されていますが、それについて日本の中小企業政策にはどんな根本理論があったのか、そして63年と99年の制定にはどのような背景があったのかを当時の社会情勢を交えながらお話しされました。
その後、1999年の制定以降、中小企業や中小企業政策の変化について話が進みました。これらの変遷を辿り、池内様が強く伝えていたのは「中小企業観の変化」です。1963年の制定当時は、中小企業とは大企業と比べて不利な立場にあり、その格差を是正するために制定されました。しかし、中小企業の経営者や経営学の研究者が長年にわたり中小企業のあり方を示してきたことにより、中小企業の存在や課題は思っている以上に多様で複雑であると認識されるようになり、中小企業への理解が進歩しました。それ以降、地方自治体や中小企業団体などが中小企業政策形成の一主体となって存在しています。その一例として、「金融検査マニュアル」や「中小企業憲章」「中小企業振興基本条例」などを挙げました。




最後に、中小企業憲章や中小企業振興基本条例は、99年改正基本法への中小企業経営者からの新たな提案であり、自らが変革の主体となることの決意表明でもあると解説しながら、今後は中小企業の経済的な役割だけでなく、地域や人々の暮らしや生活との結びつきを明確化して、社会的役割も評価していく必要があると締めくくられました。
学生たちとって、池内様の講義や問いは、中小企業の今後のあり方について深く考える機会となりました。
7月18日(金)
中小企業の国際戦略とM&A/
株式会社マイゾックス 代表取締役社長 溝口博己様
7月18日には、株式会社マイゾックスの代表取締役社長・溝口博己様が登壇し、「中小企業の国際戦略とM&A」についてご講演いただきました。
マイゾックスは、測量・土木・建築関連機器の開発・製造・販売までを手がけ、メーカーと商社の機能を併せ持つ企業です。講演では、今後の人口減少に伴い市場の縮小が予想される中で企業の成長を図るため、国際展開とM&Aを検討するようになったとお話しされました。
国際展開における課題としては、海外事業に対応できる人員の不足、為替変動リスク、現地パートナー開拓の難しさなどが挙げられましたが、同社はこれらの課題を乗り越え、事業を拡大。講義では、同じようにニッチな業種で国際展開を成功させた他社の事例も紹介されました。


中小企業のM&Aについては、近年増加しており、その背景に市場ニーズの変化や、経営者の高齢化と後継者不足などの課題があると指摘されました。マイゾックスは、2023年に宮木工業をM&Aにより子会社化しており、その経緯を説明。宮木工業が国内外に自社工場を保有していたことや、顧客層が重なっていたこと、財務体質、事業規模などを総合的に判断して、資本提携に至ったと語られました。
学生たちに対して、中小企業へ就職を検討する際には、経営者の年齢や後継者の有無、業界内でのポジションやシェア、自社独自の強み、財務状態などを事前に確認しておくと良いとのアドバイスがありました。
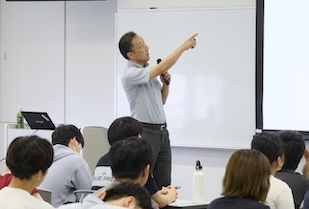



質疑応答の時間には、「信頼できるパートナー企業をどのように見つけたのか」という質問が寄せられ、溝口様は、海外の展示会で出会った企業の工場を訪問し、働く人や経営者の考え方に触れ、一緒に取り組むようになったと振り返りました。その他にも、「海外事業に携わる人材の採用基準」や「ニッチな市場で日本の半分以上のシェアを取れる理由」などの質問が投げかけられ、学生にとって中小企業の国際展開や戦略について理解を深める有意義な時間となりました。
7月25日
中小企業で働き、成長するとは/
株式会社マイゾックス 高橋和也様、梶田裕樹様、小柳奈緒佳様
7月25日には、株式会社マイゾックス様の社員3名が登壇し、「中小企業で働き、成長するとは」というテーマでご講演いただきました。
はじめに、生産開発部開発課の高橋和也様が登壇され、ご自身の入社の経緯や現在の仕事内容について説明。マイゾックスでは研修制度が整っており、高橋さんは入社後、製造工場や営業企画課、測量会社での研修を経験し、同社の「学び支援制度」を活用して測量士補の資格を取得されました。実際の業務はゼロからのスタートでしたが、「研修や学び支援制度を活用した経験が現在の設計開発業務に役立っており、会社とともに自分自身も成長できていると実感しています」と語られました。
学生たちに向けて「就職活動に正解はありません。インターンシップやオープンカンパニーなどに積極的に参加し、自分に合った企業を見つけてください」と温かいエールが送られました。


続いて登壇したのは、営業企画部の梶田裕樹様。新卒で入社後、一度は大企業へ転職し、のちに再入社したというキャリアを歩まれています。講演では、大企業を経験したからこそ見えた中小企業の良さについても語ってくださいました。


「長く働き続けられるか」「人として成長できるか」「思っていた仕事と違ったらどうしよう」といった不安を払拭できる職場だと感じ、マイゾックスへの入社を決めたと振り返る梶田様。実際に、若手から営業職として多くの仕事を任され、幅広いスキルを身につけることができたと話されます。しかしその後、「中小企業では得られない経験をしてみたい」という思いから、医療機器メーカーへ転職。ところが、大企業ならではの業務の分業や役割の狭さにギャップを感じ、最終的にマイゾックスへの再入社を選択されました。現在は、営業職で培った経験を活かし、カタログ制作やキャンペーンの企画・立案など、営業企画業務に従事されています。別の会社を経験したからこそ、広い視野で物事を捉えることを意識していると話し、現在は他部署の発言の意図が理解できるようになり、自身の発言にも説得力が増したほか、分析力の向上も実感していると語られました。
学生に向けて、「大企業が必ずしもすべてにおいて優れているとは限りません。中小企業も視野に入れて就職活動を進め、自分自身の軸をしっかり持って取り組んでください」と力強いメッセージを送られました。


最後に登壇したのは、ビジネス学部の卒業生で、営業部に所属する小柳奈緒佳様。現在の業務内容とそのやりがいについて語られました。特に、同社で初めての女性営業職であることについて、「お客様に安心感を与えやすく、ニーズを引き出しやすい」「業界内では女性営業が珍しく、覚えてもらいやすい」と話され、女性ならではの強みを実感している様子でした。
また、就職活動を振り返り、「当時は自分の進路や志望の軸が明確でなく、自己分析や業界研究の重要性を十分に理解していなかった」と話されます。転機となったのは、大学4年生の7月、「中小企業を学ぶ」で溝口社長の講義を聴いたことをきっかけに、自ら面接を依頼したことが、現在の道につながったそうです。実際に企業研究する中で、自社ブランドを持っていること、事業が社会インフラに貢献していること、競合他社が少なく優位性があること、さらにワークライフバランスやジョブローテーションの制度が整っていること、そして何より働く人の雰囲気が自分に合っていると感じたことから、マイゾックスへの入社を決意したそうです。学生たちには「仕事のどこに楽しさを感じるか考えてみてください」と締めくくられました。


質疑応答の時間では、「やりがいを感じるのはどのような時か」「中小企業から大企業へ転職する時に苦労したこと」などの質問が寄せられ、中小企業で働くことへの理解を深める、貴重な機会となりました。












