追究
2025年10月30日
高校生のためのスタートアップ心理学講座

2025年8月26日(火)長久手キャンパス741教室
心理学部の教員による高校生対象の一日体験講座を実施。
専任教員が各分野を解説し、受講生は心理学の魅力を体感しました。
愛知淑徳大学心理学部では、2025年8月26日(火)に「高校生のためのスタートアップ心理学講座」を開催しました。心理学に関心を持つ高校生を対象に、専任教員がそれぞれの専門分野から心理学の魅力をわかりやすく紹介。心と社会、発達、臨床、生理・認知など、幅広いテーマを体験することで、心理学の多様性と奥深さに触れる一日となりました。当日の講座内容をダイジェストでお届けします。


1限 心理学とは/小川 一美先生


「心はどこにあるのか?」という問いかけから、小川一美先生の講義は始まりました。受講生の中には胸を指す人もいれば、頭を指す人もいて、その答えはさまざまです。実際、過去の偉人であるアリストテレスは心が心臓にあると考え、ヒポクラテスは脳にあると考えていたと言われていますが、いまだに結論は出ていません。目で見ることも、触れることもできない「こころ」を、私たちはどう捉えるべきなのでしょうか。心理学はその答えを「観察可能な行動」から探っていく、「人間の行動の法則性を研究する科学」です。科学である以上、「実証性」「客観性」「再現性」が求められます。仮説を立て、データを集め、分析し、考察するという流れを通じて、多くの人に共通する行動の法則を見つけ出していきます。
研究手法も多彩で、実験法、調査法、観察法、面接法など、さまざまなアプローチが用いられます。心理学の領域は広く、社会心理学、発達心理学、生理心理学、認知心理学、臨床心理学など、多様な分野が存在します。たとえば「記憶力を高める方法」や「推し活が人に与える影響」といった身近なテーマも、心理学の研究対象になり得るのは興味深い点です。
本学では、多様なテーマを切り口に、自分の関心に合った学びと出会うことができると、小川先生は話します。心理学を学ぶプロセスで得られるのは、「人間の行動と心についての理解力」「問題発見・解決力」「実証的分析力・論理的思考力」「コミュニケーション力」など。受講生にとって、大学で広がる心理学の世界に触れられた、貴重な時間となったことでしょう。
2限 発達心理学/久保 南海子先生


久保南海子先生は、発達心理学という分野において、ヒトの一生を通じた発達と心の変化について講義をおこないました。久保先生は、発達とは単に成長することではなく、生まれてから死に至るまでのすべての変化を指すものであると説明。その対象は赤ちゃんから高齢者まで幅広く、感情や記憶、友人関係、家族、社会活動、生きがいなど、研究テーマも多岐にわたると話しました。
講義の中心となったのは「感情の発達」です。受講生はまず、日頃抱く感情を自由に書き出し、それを「快―不快」「覚醒―眠気」という2軸に整理するワークに取り組みました。続いて、エクマンの基本6感情やラッセルの感情円環モデルを紹介し、感情を分類・理解する多様な方法を学びました。
さらに、赤ちゃんが生まれた直後に示す「自発的微笑」から、親しい人に向ける「社会的微笑」へと発達する過程や、悲しみ・嫌悪・驚き・恐れといった感情の出現を例に、認知の発達とともに感情が豊かになっていく様子を具体的に解説しました。また、高齢期において肯定的感情が増し、否定的感情が減少する「ポジティビティ効果」や、ヒトとチンパンジーを比較して、社会的微笑の進化的特徴を紹介し、「心の進化」という視点からも考察を広げました。
受講生にとって、自分の感情を振り返りながら、人間の心の変化を多角的に捉える貴重な機会となったことでしょう。
3限 社会心理学/平島 太郎先生


3限目は、平島太郎先生による社会心理学の講義が行われました。テーマは「人と人とが互いに影響を与え合うことで、社会がどのように形づくられていくのか」。平島先生は、心を個人の内側、社会を個人の外側と捉える一般的なイメージに触れながら、社会心理学はその両者を結びつける学問であると説明しました。
講義の前半では、「人間の心の特徴」として、私たちが他者の心を過剰に読み取ってしまう傾向に注目。無機質な図形が動く映像を見て、受講生がその内容を書き出すワークを行い、人は無機質なものに対しても自動的に意図や感情を読み取ってしまうことを体感しました。さらに、「親切心は味覚を変えるのか?」という心理学実験を紹介し、心を敏感に感じ取りすぎる人間の特性についても触れました。
後半では、「複数人が集まると何が起きるのか」というテーマに移り、同調や社会的現実の形成について解説。友人に合わせてしまう身近な例から、誰も欲しくないバッグを全員が持ってしまう現象、さらには新型コロナ禍での「トイレットペーパー買い占め事件」まで、集団の中で互いに心を読み合った結果、個人の考えの単純な足し算では説明できない現実が生まれる過程が紹介されました。これは「社会的現実」と呼ばれ、私たちが日常的に生きている現実そのものであると平島先生は話します。
講義の最後には、公共の場での事例として「体調が悪そうな人に席を譲れない」状況が紹介されました。これは個人の意識やマナーの欠如ではなく、互いに他者の心を読み合うことで生じる状況によるものであり、誰もが影響を与え合う存在であることを理解する重要性が強調されました。
受講生にとって、社会心理学の視点を通じて自分自身と他者、そして集団や社会との関わりを新たに考えるきっかけとなり、人間理解の奥深さを感じられる時間となったことでしょう。
4限 臨床心理学/西出 隆紀先生


西出隆紀先生による臨床心理学の講義では、一般的にイメージされがちな「心理テスト」や「カウンセリング」と、専門家が実際に用いる心理検査や心理療法との違いをはじめ、臨床心理士や公認心理師がどのように人々を支援しているのかが具体的に語られました。
講義の前半では、臨床心理学の起源や定義について説明がありました。臨床心理士の業務として「心理アセスメント」「心理面接」「地域援助」「研究活動」が紹介され、国家資格である公認心理師の役割についても解説されました。
受講生に身近な例として、血液型占いやインターネット上の心理テストが取り上げられ、誰もが「当たっている」と感じてしまうバーナム効果が実演されました。そのうえで、妥当性・信頼性・標準化を備えた本物の心理検査との違いが強調されました。心理検査は、面接だけでは捉えきれない無意識の側面に迫ることができ、心理療法の基盤となります。
また、催眠による指先の動きを体験する時間も設けられ、心理療法の不思議さと実際のプロセスを身近に感じる機会となりました。
講義の後半では、心の病と健康の境界が必ずしも明確ではないことが示され、不安障害や発達障害、心因性の症状など、多様な課題に臨床心理学がどのようにアプローチしているのかが語られました。西出先生は、臨床心理学が医療・福祉・教育・司法・産業など幅広い分野に関わり、人々の生活を支えていることを強調しました。
受講生にとっては、日常的に触れる「心理テスト」と専門的な心理検査との違いを知り、心理士の仕事の奥深さや社会的な役割を理解する貴重な時間となったことでしょう。
5限 生理・認知心理学/成澤 元先生
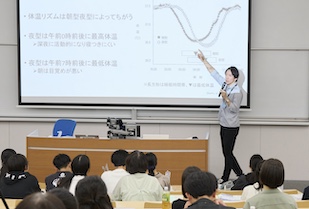

成澤元先生による生理・認知心理学の講義では、「リズム」という切り口から心と体のつながりについて学びました。好きな人を前にするとドキドキしたり、不安で眠れなくなったりするように、心の状態は身体に表れます。心理学が人間理解において身体を欠かせない要素とする理由を、食欲や睡眠の仕組みから考えていきました。
お腹が空けば食べる行動が促されますが、空腹感やお腹が嗚るのは胃から分泌される「グレリン」というホルモンの働きによるもので、その分泌リズムは体内時計や生活習慣に影響されます。こうした日内変動はたくさんあり、睡眠覚醒のリズムと心の深い関係も一例です。夜は「メラトニン」が分泌され眠くなり、朝日を浴びると「セロトニン」によって目覚めるという仕組みを持ち、セロトニンには気分を調節する役割もあることが紹介されました。
さらに、深部体温の変化と睡眠の関係については、入浴のタイミングや朝型・夜型の体質が眠りに影響することが示されました。一方で、睡眠不足の影響についても触れられました。世界記録に挑戦した断眠の事例では、断眠日数ごとに妄想や集中力の低下など深刻な変化が現れることが説明され、受講生は睡眠の重要性を深く理解している様子でした。また、慢性的な睡眠不足は眠気の自覚がないままパフォーマンスを低下させ、日本では年間20兆円の経済損失につながっているという事実も紹介されました。これから受験勉強が忙しくなる受講生に向けて、成澤先生は「学習内容を定着させるには睡眠が不可欠であり、睡眠時間を削る努力は逆効果である」と強調しました。
心と体は複雑なリズムで結びついており、そのリズムを理解し整えることこそが、健やかな生活や学びの基盤となることが理解できたはずです。受講生にとって、日常に直結するテーマを科学的に捉える貴重な体験となったことでしょう。
心理学部の紹介/吉崎 一人先生


吉崎一人先生による心理学部紹介では、学びの特徴や卒業後の進路について説明がありました。本学心理学部は、卒業時の学生満足度で学内1位を誇り、21名の専門教員のもと、幅広い領域を学ぶことができます。
1・2年次には基礎を徹底的に学び、3年次からはゼミで専門的な研究を深め、4年次には卒業論文として研究成果をまとめます。30年以上の歴史と充実した演習施設を備え、科学的な知見や研究方法を段階的に習得できる点が大きな特徴です。他学部と比べ大学院進学率も高く、公認心理師、臨床心理士、研究者として活躍する卒業生も多数います。吉崎先生は「本学で心理学を勉強してもらえるとうれしいです」と語り、受講生にとって心理学の魅力を存分に感じられる一日となったことでしょう。












