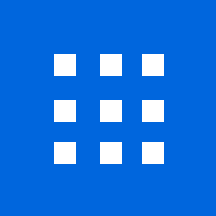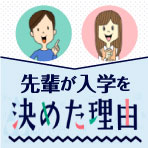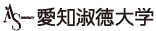交流文化学部 交流文化学科 林 大策

林 大策
交流文化学部
交流文化学科
「観光」によってまちの魅力をいかに輝かせるか。
プロフィール
- 学歴
-
- 1991年3月:立教大学法学部法学科卒業
- 2004年3月:多摩大学院経営情報学研究科修了 経営学修士
- 職歴
-
- 1991年4月〜2014年3月:中部日本放送株式会社勤務
- 2014年4月:愛知淑徳大学交流文化学部准教授
- 2017年4月:愛知淑徳大学交流文化学部教授
放送局に勤めながら、大学院でコミュニティビジネスを追究した林先生。観光まちづくりを専門とし、現在は愛知県常滑市や一宮市、新城市、岐阜県七宗町などの観光政策にも携わっています。ゼミでは「何でも見てやろう」をモットーに、学生が五感で探究する「実践の場」を重視。一人ひとりの主体的な学びを後押ししています。
「観光が日本を救うかも知れない!?」
これは、私がオープンキャンパスなどで高校生向けの授業を行うときの講義のタイトルです。日本では、ここ数年、テレビや新聞で「観光」に関する話題を見ない日がないほど「観光」が注目されています。日本を訪れる外国人観光客は、ここ10年で約4倍となり、エアラインやホテルなど観光関連企業だけでなく、「爆買い」に象徴されるように、デパートやドラックストアの売り上げにも寄与してます。さらには、人口流失、少子高齢化という課題を抱える地方においても、観光施策によって課題を解決しようという取り組みがおこなわれています。
このように前述のタイトルは「観光産業が日本経済を支える基幹産業のひとつになるかも知れない」という意味なのです。
しかし、一方で、タイトルに「?」がついているのは、「オーバーツーリズム」という言葉に代表されるような「観光公害」の問題も増えてきているからです。京都では、市バスなどが時刻通りに運行できなくなっていたり、鎌倉では、観光の魅力でもあった「食べ歩き」がゴミのポイ捨が増えすぎて自粛条例が制定されました。スペインのバルセロナでは、ホテル、民泊の増加により市内の賃料が急激にあがってしまうという現象も起きており、観光客を減少させようという動きもでています。観光地として人気になることは全てよいことばかりではないのです。「訪れたい」「住みたい」がバランスよく調和できるまちを目指すことが理想です。このようなまちづくりを考えることが、私の専門である「観光まちづくり」です。
日本が観光大国となり「誰もが観光と関わらざるを得ない時代」がやってくる可能性が大きくなっています。学生には、将来の進路として観光産業に進むか否かに関わらず観光の知識を持った社会人になって欲しいですし、自分自身の経験から「学び」が人生を切り開くということも伝えていきたいと思います。
主要著書・論文
-

物語のあるまちに旅にでよう
リベラル社(2012年)
-
「観光」を学ぶ「場」としての被災地・気仙沼の可能性
愛知淑徳大学交流文化学部 愛知淑徳大学論集ー交流文化学部篇 第8号 23-42(2018年)
-

一宮市産業観光プロモーション調査レポート
一宮産業観光プロモーション事業推進協議会(2019年)
-

名古屋いい店うみゃ〜店
(共著)文藝春秋(2005年)
(2020年1月 取材)