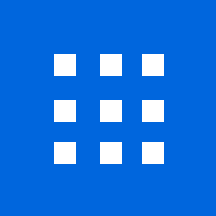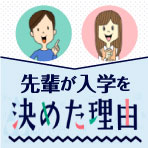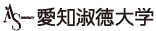人間情報学部 人間情報学科 牧 勝弘

牧 勝弘
人間情報学部
人間情報学科
「音」に対する研究を通じ、学生たちの思考力や主体性を育んでいきたい。
プロフィール
- 学歴
-
- 1995年3月:法政大学工学部電気工学科計測制御専攻卒業
- 1997年3月:北陸先端科学技術大学院大学情報科学研究科情報処理学専攻博士前期課程修了
- 2000年3月:東京工業大学大学院総合理工学研究科知能システム科学専攻博士後期課程修了 博士(理学)
- 職歴
-
- 2000年4月~2002年3月:同志社大学工学部知識工学科ポスト・ドクター
- 2002年4月~2005年3月:NTTコミュニケーション科学基礎研究所人間情報研究部リサーチ・アソシエイト
- 2005年4月~2010年3月:NTTコミュニケーション科学基礎研究所人間情報研究部リサーチ・スペシャリスト
- 2010年4月~2011年9月:情報通信研究機構ユニバーサルコミュニケーション研究所 超臨場感映像研究室エキスパート研究員
- 2011年10月現在:愛知淑徳大学人間情報学部人間情報学科准教授
「音」のさまざまな研究に力を注いでいる牧准教授は論文が日本音響学会の名誉ある賞に輝くなど、研究成果を着実に積み重ね、音に関連する専門分野の発展に貢献しています。そんな牧准教授が学生たちに伝えているのは「失敗をおそれず研究を真剣に楽しもう」ということ。そして、そのプロセスから論理的思考力、分析力、問題発見能力などを身につけてほしいと語り、学生たちが自ら社会人へと成長できるよう後押ししています。
研究テーマは、脳の中で音が処理されるしくみの解明。
私の専門は「聴覚神経科学」「音響工学」です。我々の聴覚には、音の方向を判断したり、音楽を楽しんだり、音声を理解するといった役割があります。このような聴覚の機能は、我々の日常生活に欠かせません。例えば、音の方向が分からなければ、車などの音を発する危険物から逃れそびれてしまいます。また、音声が理解できなければ友達とコミュニケーションをとることもできません。さらに、音楽がなければ映画の感動は半減し、日常生活は今よりも味気ないものになるでしょう。
こうした音の処理はすべて、我々の脳の中でおこなわれています。私の研究では、このような音を処理する脳のしくみを解明していくことが一つの大きなテーマとなっています。脳の中を流れる音情報の解析に適した計算機シミュレーション、脳の電気活動から脳の処理を読み取る生理実験、および人の知覚特性を調べることができる心理実験等の実験手法を駆使してこの問題に取り組んでいます。

思い出深い曲を聞いた時に涙が出る理由とは。
皆さんの中で、卒業式の曲など思い出深い曲を聞いた時に涙を流した経験のある人は多いのではないでしょうか?逆に、すごくきれいな映像、あるいは景色を見た時に涙を流した経験のある人は少ないと思います。このように音は感情と強く結びつきやすい性質を持っており、これは感情を司る脳領域と音を処理する脳領域とが強く結びついているからだと考えられています。最近では、こうした関係に興味があり、研究を進めています。
より「本物」に近い音の再生をめざすモノづくり研究も。
一方で、音に関するモノづくり研究についても取り組んでいます。現在の5.1チャンネルなどのスピーカーシステムでは、鮮明な音や迫力のある音を楽しむことはできますが、まさにそこで演奏しているかのような「本物」の音を再生することはできません。現状では、スピーカーの音を聞いて、本物の楽器の音、あるいは本物の歌手の歌声であると勘違いする人はいないでしょう。私のもう一つの研究テーマとして、次世代音響システムに関する研究が挙げられます。「人」の演奏する楽器音や歌声の空間音響特性を調べることで「生」を感じさせる要因を明らかにし、さらに、それを再生可能なマルチアレイスピーカーの製作もおこなっています。この研究が進めば将来的にCDプレーヤーなどでより「本物」に近い音を再生することができるかもしれません。
主要著作
-

音響サイエンスシリーズ「聴覚モデル」
日本音響学会編 森、香田編著 コロナ社 (2011年)
(「第6章 聴覚中枢神経系の生理現象とそのモデル」 PP168-194) -

Auditory signal processing: physiology, psychoacoustics, and models
edited by D. Pressnitzer, A. De Cheveigné, S. McAdams and L. Collet,
Springer Verlag(2005)
(Akagi, Mと共著 "A computational model of cochlear nucleus neurons" PP84-90)
(2015年7月 取材)