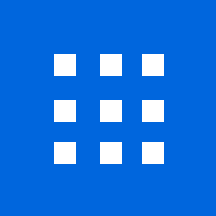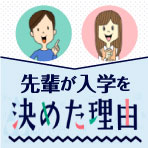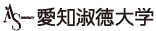文学部 国文学科 竹内 瑞穂

竹内 瑞穂
文学部
国文学科
近現代文学を通して「違い」のおもしろさ、尊さに出会う。
プロフィール
- 学歴
-
- 2004年3月:横浜市立大学国際文化学部日本アジア文化学科卒業
- 2006年3月:名古屋大学大学院文学研究科日本文化学専攻博士前期課程修了
- 2009年3月:名古屋大学大学院文学研究科日本文化学専攻博士後期課程満期退学
- 職歴
-
- 2009年4月:東海高等学校 国語科教諭
- 2010年4月:愛知淑徳大学文学部 助教
- 2015年4月:愛知淑徳大学文学部 准教授
- 2021年4月:愛知淑徳大学文学部 教授(現在に至る)
大学2年次に読んだ谷崎潤一郎の作品がきっかけで、近現代文学の研究に力を注ぐようになった竹内先生。時代をこえて新鮮なおもしろさを放ち続ける文学作品やその背景にある文化史を探究し続けています。「わからないことを楽しもう」と授業やゼミを通して学生たちに語りかけ、人と人の多様な「違い」を理解し合うことの大切さを伝えています。
私の研究テーマを一言でいえば、「近代日本の〈逸脱〉をめぐる文学・文化史」ということになるでしょうか。これまでも大正期の〈変態〉概念や、昭和初期の〈エロ・グロ・ナンセンス〉ブームなどを分析の対象としてきました。
このようなテーマを手がけるようになったそもそものきっかけは、大学生時代に何気なく手にとった谷崎潤一郎の初期作品集でした。明治末に書かれた古い作品なのに、そこには現代の我々が読んでも衝撃を受ける逸脱的なエロスと絢爛な美が溢れていたのです。近代文学=真面目・古くさい・重苦しいという自分の印象が、高校までの国語の授業によって培われた固定観念に過ぎなかったことに気づかされた瞬間でした。
以後、いわゆる王道をはずれた文学を読み漁るなかでわかってきたのが、谷崎に限らず近代の多くの作家たちが〈変態〉的なテーマを積極的に描こうとしていたという事実です。「変態」の語源ともなった変態心理学や変態性欲論は、当時最先端の精神医学・心理学の理論でした。作家たちは新時代の流行に乗るため、さらには新たな芸術的なイマジネーションを生み出す触媒として、それら〈変態〉を自らの文学に取り入れていたのです。
文学に限らず、私たちは〈逸脱〉したものに出会うと、反射的に忌避してしまうことがあります。しかし、それらと向かい合うことでみえてくること、学べることも少なくないはずです。私の研究は「違いを共に生きる」という本学理念と、根本で繋がっているように思います。
主要著書・論文
-

東海の異才・奇人列伝
(共著)風媒社 59頁ー64頁 2013年4月
-

「変態」という文化―近代日本の〈小さな革命〉
ひつじ書房 2014年3月
-

〈変態〉二十面相―もうひとつの近代日本精神史
(共著)六花出版 1頁ー19頁、193頁ー212頁 2016年9月
-

文芸雑誌『若草』―私たちは文芸を愛好している
(共著)翰林書房 22頁ー23頁、204頁ー226頁 2018年1月
(2021年2月 取材)