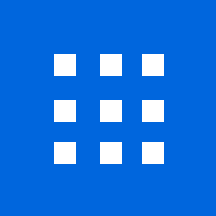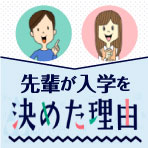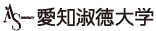食健康科学部 食創造科学科 吉田久美

吉田久美
健康医療科学部
健康栄養学科
植物の色を探究し、その不思議な構造を解き明かす。
プロフィール
- 学歴
-
- 1980年3月:名古屋大学農学部 卒業
- 1982年3月:名古屋大学大学院農学研究科博士前期課程 修了
- 1992年7月:博士(農学)名古屋大学
- 職歴
-
- 1982年3月:天野製薬(株)研究部
- 1988年4月:椙山女学園大学家政学部 助手
- 1994年9月〜1995年9月:ドイツコンスタンツ大学生物学部 客員研究員
- 2000年4月:名古屋大学大学院人間情報学研究科 助教授
- 2010年4月:名古屋大学大学院情報科学研究科 教授
- 2023年4月:名古屋大学 名誉教授、愛知工業大学工学部 客員教授
- 2024年4月:愛知淑徳大学食健康科学部 教授(現在に至る)
生き物が創り出すあらゆる物質が対象の天然物化学を専門とし、植物色素の研究に打ち込む吉田先生。花や豆などの色素の謎に迫り、定説を覆す新たな研究成果を発表するなど、第一線を走り続けています。「身近なところに、不思議な現象があふれています。『なぜ?』という疑問から、新たな学びを広げてほしい」と吉田先生は学生にエールを送ります。
本年4月1日に、新しくできました食健康科学部食創造科学科に着任いたしました。専門は、天然物化学・生物有機科学です。とてもひろい分野ですが、いわゆる天然に存在する機能性分子の化学構造や機能の研究で、中でも、「アントシアニン」という植物色素の研究をずっと行ってきました。現在、体に良い、というようなキーワードで「大豆ポリフェノール」とか「ブルーベリーアントシアニン」という言葉を聞かれたことがあるかと思います。そのような分子が研究対象です。アントシアニンは花の色素でもあり、ほとんどの青色の花の色素はアントシアニンです。具体的には花の色素の研究、なぜこの花は青いのか、なぜこれは赤いのかということの解明です。
アントシアニンの研究の歴史はとても古く、19世紀末にはアジサイの色を対象に始まっていました。20世紀の初めには、ドイツの研究者が赤いバラと青いヤグルマギクの花の色素が同じであるにもかかわらず色が違うのは、バラの細胞が酸性、ヤグルマギクの細胞はアルカリ性だというpH説を出しました。これに対して日本の研究者はたくさんの花びらのpHを測定してどれも弱酸性であることを根拠に、青色の花はアントシアンの金属錯体であるという説を出しました。この論争は長く続いてきたのですが、最終的に1992年に私たちの研究グループが、青色のツユクサの花の色素の構造を解明して金属錯体である証拠を報告しました。さらに、空色西洋アサガオは、ツボミは赤く咲くと空色に変化しますが、それぞれの色の花びらに極く細いpH電極を刺して測定することにより、これがpH変化によることも1995年に証明しました。
最近は、「アジサイがなぜ色が移り変わり易いのか」や、「赤い小豆の皮にはアントシアニンはほとんど含まれておらず、水に溶けない紫色の新しい色素があること」などを明らかにしました。
主要著書・論文
-

「アジサイの教科書」
(分担執筆)緑書房 2024年9月
-

食用豆種皮の色素「豆類の百科事典」
(共著)朝倉書店 2024年5月
-

植物におけるポリフェノールの存在意義と生合成・機能性「ポリフェノールの科学」
(共著)朝倉書店 2023年11月
-

なぜ青いバラは咲かないのか、︱アントシアニンによる多彩な花色の発現機構︱「植物の超階層生物学:ゲノミクス×フェノミクス×生態学でひもとく多様性」種生物学シリーズ(種生物学会編)
(共著) 文一総合出版 2023年8月
-

Chemical and biological study of flavonoid-related plant pigment: current findings and beyond
Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry, Volume 88, Issue 7, July 2024, Pages 705–718
(2024年10月 取材)