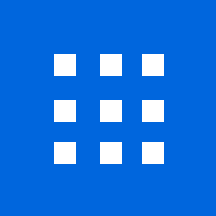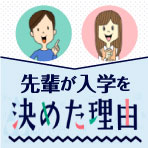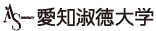心理学部 心理学科 平島 太郎
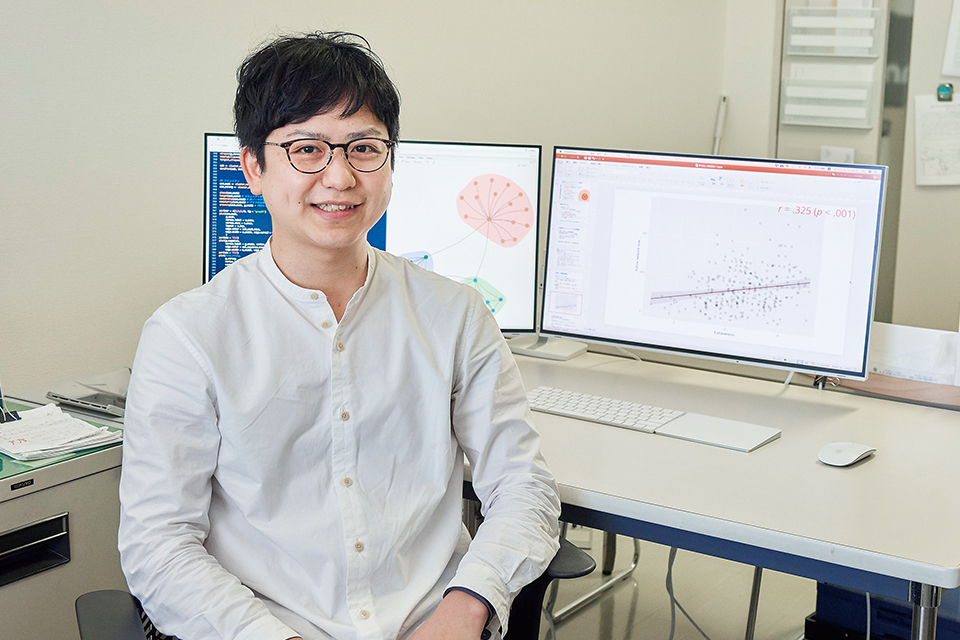
平島 太郎
心理学部
心理学科
目には見えない人と人のつながりをとらえ、現代社会の課題に迫る
プロフィール
- 学歴
-
- 2010年3月:名古屋大学教育学部心理発達科学科卒業
- 2012年3月:名古屋大学大学院教育発達科学研究科博士前期課程修了
- 2015年3月:名古屋大学大学院教育発達科学研究科博士後期課程単位取得満期退学
- 2015年4月:名古屋大学大学院教育発達科学研究科技術補佐員(博士研究員)
- 2018年4月:愛知淑徳大学心理学部講師(現在に至る)
社会心理学を専門とする平島先生は、社会を形成する人と人のつながり「社会的ネットワーク」に着目し、日常生活に身近なテーマで研究を深めています。ゼミでは学生の興味を尊重しながら個々の研究をサポート。議論を重視し、互いに意見を伝え合う力を養っています。「心や人間関係などの測定と分析を通じ、よりよい社会づくりに必要なものを探究したい」と語る平島先生。その熱意は学生の向学心も刺激しています。
「友だちの数は何人?」身の回りの人間関係を思い浮かべると、すごく顔が広い人から、少数の人との付き合いを大事にする人まで、さまざまな人がいます。では、このような友人・知人の数の違いは、どのような心理的・社会的要因によって規定されるのでしょうか? 私は社会心理学や社会的ネットワークを専門とし、この研究テーマに取り組んでいます。
研究というには素朴すぎるようにも思えるテーマですが、私は2つの重要な点があると考えています。第一に、研究テーマの延長には「人間とは何か」という興味深い問いがあることです。人間の社会的ネットワークのサイズ(友人や知人の数≒群れの大きさ)は、チンパンジーなど他の霊長類に比べて大きいことが知られています。「群れ」が大きくなるほど個体間の関係も複雑になりますが、なぜ人間は多数の他者と社会を形成できるのでしょうか。これに答えることは、心理学に留まらない重要な問いの一端を明らかにすることとなります。
第二に、この研究テーマが社会における多様性の問題とつながっている点です。政治的態度の違いなどに基づく社会の分断は、大きな社会問題です。付き合う人数が多くなるほど、多様な他者と関わることとなります。友人・知人の数に関与する要因を明らかにすることができれば、多様な他者といかに共生できるかに関するヒントを得られると考えています。研究を通じ、異質な他者に対しても寛容であるような多様性のある社会作りに貢献したいと考えています。
「友だちの数が何で決まるか?」という日常生活の中での素朴な疑問を、より広い問いや社会問題と結びつけて考えられるようになることは、私たち人間自身を研究対象とする心理学を学ぶことのよさでもあります。「他者の心を読む」ことだけを目指しているわけではない幅広い心理学のおもしろさや重要性を、学生はもちろん一般の方々にも知ってほしいと思っています。
主要著書・論文
-
他者表情からの情動認知と社会的ネットワーク・サイズ
東海心理学研究
(2017)11、29ー39 -
社会的ネットワークの構成と態度の両価性の関連
名古屋大学大学院教育発達科学研究科紀要(心理発達科学)
共著(2014)61、105ー114 -
態度の両価性が行動意図の形成に及ぼす影響
実験社会心理学研究
共著(2014)54(1)、1ー10・doi:10・2130/jjesp・1215 -

心理学概説 第2版
ナカニシヤ出版
(2019)pp・83ー91 -

心理学・社会科学のための構造方程式モデリング—Mplusによる実践—
ナカニシヤ出版
(2018)pp・135ー144 -

社会的ネットワークを理解する
北大路書房
(2015)pp・181ー216
共編
(2019年5月 取材)