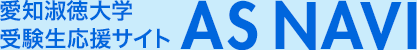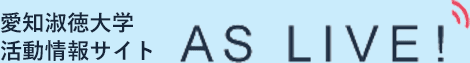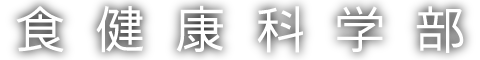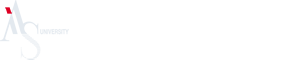食創造科学科

食創造科学科は、「食品開発」を「食創造」として捉え、それを実践的に学びます。食品の成分分析やマーケティングリサーチに取り組み、食に関わる分析力を養成。また、味や食感、栄養などの「食の魅力」を科学的な側面と、技術的な側面から探究し、食品の企画につなげます。デコレーションやコーディネートなどの食品開発後のアプローチについても学び、食に関する多様かつ専門的な知識を修得していきます。


身につく力
- 食品の効能、おいしさの「わけ」を多角的に分析する力
- 新しい食品、食の在り方を理論・実践の両面から提案する力
- 健康で心が豊かになる食生活を実現する力
食材の機能と効能を探究し、健康社会に寄与できる人材を育成
-
東洋医学には「未病(みびょう)を治す」という言葉があります。これは病気の症状が現れる前に治す、病気にならないように健康の維持増進に努めましょうという意味です。そのためにも日頃からバランスの良い食生活について考えることが大切です。
日常の食卓に供される食材には、食べ物という範疇を超えて漢方薬として使われているものが多くあり、これらは薬膳料理にも使われます。例えば、湯豆腐に添えられているショウガ、ウナギの蒲焼に欠かせないサンショウ、ぜんざいの原料のアズキは、中国最古の薬物書である『神農本草経(しんのうほんぞうきょう)』に記載があり、それぞれ薬としての効能があります。これらの食材を「薬用食物」といい、上手に組み合わせることにより薬効が増強したり、味が良くなったりします。
食創造科学科では、多様な食材を東洋医学の「医食同源」の考え方に基づいて配合し、健康の維持や増進、病気の治療までをおこなう「薬膳」について学ぶことができます。食材のもつ薬としての効能を活かし、美味しさや食べやすさにもこだわった新しいメニューや調理法の開発もおこなっていきます。西洋医学における栄養学的な知識とあわせて総合的に「食」を探求し、健康について考え社会貢献できる人材を育成します。 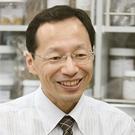
小松 一 教授
博士(薬学)
専門分野は薬膳学、漢方薬学、東洋医学
東洋医学には「未病(みびょう)を治す」という言葉があります。これは病気の症状が現れる前に治す、病気にならないように健康の維持増進に努めましょうという意味です。そのためにも日頃からバランスの良い食生活について考えることが大切です。
日常の食卓に供される食材には、食べ物という範疇を超えて漢方薬として使われているものが多くあり、これらは薬膳料理にも使われます。例えば、湯豆腐に添えられているショウガ、ウナギの蒲焼に欠かせないサンショウ、ぜんざいの原料のアズキは、中国最古の薬物書である『神農本草経(しんのうほんぞうきょう)』に記載があり、それぞれ薬としての効能があります。これらの食材を「薬用食物」といい、上手に組み合わせることにより薬効が増強したり、味が良くなったりします。
食創造科学科では、多様な食材を東洋医学の「医食同源」の考え方に基づいて配合し、健康の維持や増進、病気の治療までをおこなう「薬膳」について学ぶことができます。食材のもつ薬としての効能を活かし、美味しさや食べやすさにもこだわった新しいメニューや調理法の開発もおこなっていきます。西洋医学における栄養学的な知識とあわせて総合的に「食」を探求し、健康について考え社会貢献できる人材を育成します。
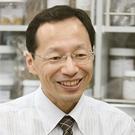
-
小松 一 教授
博士(薬学)
専門分野は薬膳学、漢方薬学、東洋医学
食創造科学科の特色
食に関する多領域を
横断的かつ専門的に学ぶ食について科学的な根拠から学ぶことを土台に、「食品」「調理」「健康」「栄養」「食文化」「食創生」という、食に関する多様な領域についての知識を修得。食をあらゆる視点から捉え、新たな食を生み出す発想力へとつなげます。
さまざまな機関と連携し
食創造を実践的に学ぶ本学のコミュニティ・コラボレーションセンター(CCC)との連携や、ゼミ活動、コンペティションなどの機会を利用し、食品開発や成分分析などに挑戦。実践を通じて、食創造について生きた学びを得ることができます。
実験・実習で実践力を磨く
最新の学修・研究食品成分を調べる最新機器を設置した実験室や、食品開発などで用いられる、おいしさを評価する官能評価室、地域食やテーブルコーディネートなど、食卓美学を研究する実習室といった、先進的な学修・研究環境が整っています。
体験・経験から理解につながる学び
加工食品の試作に挑戦
科目:食品加工学実習食品加工の原理や技術を修得し、食品加工の意義、保存・貯蔵の特性について学びます。缶詰食品やレトルト食品などの加工食品を試作・製造し、実践を通じて技術を修得します。また、食品加工による食材の成分変化を確認し、加工食品に対する品質評価方法を学びます。
さまざまな機関と協働し、食創造プロジェクトに挑戦
■ゼミで食品開発に挑戦
■新しい地域食の企画・開発
■メニュー提案や食品開発のコンペティションを開催
■栄養だけでなくおいしさにもこだわった企画食品を学内で提供
■オリジナルのお菓子や加工食品(カレーなど)を開発
■コミュニティ・コラボレーションセンターと連携した食育や食品開発
※記載内容は構想中であり、変更になる可能性があります
レトルト食品の開発プロセスを学ぶ
食品メーカー・イチビキ株式会社の方をゲストスピーカーとしてお招きし、レトルト食品の開発について講演いただきました。その後、タイアップして「和風ポトフ」を開発。レシピをもとに試作し、製造へとつなげました。また、印刷会社の方にパッケージデザインや食品表示について講演いただき、学生たちがデザインを考案しました。

4年間の学び(2025年度)
 |
|---|

|

|

|
|---|---|

|

|
【食品開発】学びの流れ
PICKUP!科目詳しく読む
食品分析学・食品分析学実験
食品は、多くの異なる成分が含まれています。それぞれの成分に機能性があり、それらを分析する手法も多様です。この講義では、食品の分析に現在最も利用されている、機器分析的手法を中心に学びます。実験では、クロマトグラフィーによる色素などの成分の分離と最新機器による分析を実施します。授業を通じて、様々な分離や分析方法を知ることや、得られたデータを解析する力を養います。

食マーケティング論
製品・価格戦略やプロモーションなど食のマーケティングと、消費者行動・企業行動の関わりを経営学・社会学・行動科学の側面から学修します。「地産地消」や「食を活かしたまちづくり」の事例にもふれ、理解を深めます。
食文化論
日本や世界の食文化について、地域や宗教、気候、歴史などの背景を踏まえながら、どのように関わり、それぞれが独自の食文化を発展させてきたのか理解を深めます。食の多様性や創造性を実例をあげながら学んでいきます。
食空間・コーディネート実習
食空間の基本理論や演出の必要性、テーブルマナーなどの基礎知識を学び、世界や日本の食事文化を実践的に理解します。シュガークラフトなどのお菓子やお料理をコーディネートする上での豊かな食空間を創造する力を身につけます。

施設・設備
1号棟の4・5階に食創造科学科の専用フロアを整備。最新の設備が整った、実習室・実験室の他、専用ラウンジなども設置されています。
 1号棟外観写真
1号棟外観写真
 精密機器室
精密機器室 テーブルコーディネート実習室
テーブルコーディネート実習室
 培養室
培養室 官能評価室
官能評価室 食品加工実習室
食品加工実習室
資格・免許
取得できる資格・免許
- 食品衛生管理者任用資格*
- 食品衛生監視員任用資格*
- 司書
- 学芸員
* 任用資格:採用後、特定の業務に任用される時に必要とされる資格
取得を支援する資格など
- フードコーディネーター3級
- 食生活アドバイザー®3級
- TALK食空間コーディネーター®3級
- 惣菜管理士3級
- 初級食品表示診断士
- 登録販売者
- 日商簿記検定3級
- 三級知的財産管理技能士
活躍が期待される卒業後の進路
食創造科学科で養える食に関する総合的な知識・技術を活かせるのは、食品業界だけに留まりません。「食」をコンテンツとして扱う業種は多種多様で、食に関する記事を取り上げる出版業界や食品関連企業に融資やコンサルティングをおこなう金融機関、食をキーワードに地域活性化をおこなう地方公務員など、活躍が期待される場は想像以上に広がっています。