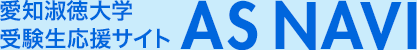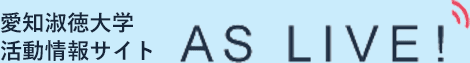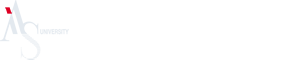式辞
2024年度(令和6年度)卒業式 学長式辞
学長の島田です。卒業生の皆さん、本日はおめでとう。心から皆さんの門出の日をお祝いいたします。また、両キャンパスにお集まりいただいた保護者の皆さまにも、今日の佳き日を迎えられたことに、深い祝意と感謝を申し上げたいと思います。
本来ならば、この晴れやかな旅立ちの日を、国際会議場の大ホールの式典で、盛大に祝うはずでした。ところが大会議場の改修工事が決まり、本学卒業生の大勢の規模をゆったりと入れられる適切な施設がただちに見つかりませんでした。
数年前に新型コロナウイルス感染が広まった時期、皆さんの先輩たちは、それぞれ所属する長久手または星が丘のキャンパスで学科、専攻ごとの卒業式を行いました。こじんまりとしてはいるけれど、4年間ゼミや教室を共にした者同士が和気藹々と集まった式典は、思いのほか、卒業生には評判のいいものでした。それならば今回もその良き前例に倣って、全卒業生が一同に会した式典とはまた一味違った、所属キャンパスでの学科・専攻別の卒業式を執り行おうということになった次第です。
さて、この式典は、卒業生の皆さんに、私が学長として、お祝いのはなむけの言葉を語る場でもあります。旅立つ皆さんに、これから先の人生の旅の折々に少しでも思い出してもらいたいことを話したいと思います。
10年ほど前、「障害者差別解消法」という法律が施行されました。福祉貢献学部の皆さんはよくご存じだと思いますが、この法律は身体障害、精神障害、知的障害などの障害者が、社会から分け隔てられることなく、健常者の人々と互いを尊重し合いながら共生する社会を築いて行く、という趣旨の法律です。具体的には、行政や民間企業などが障害者に対して不当に差別することを禁ずる、とか、障害者から社会的に自分たちを隔てる壁を取り除いてほしい、と希望が出た場合、過重な負担にならない限り、希望に添うように努力する、といった内容です。例えば、耳が聞こえない、あるいは目が見えないという受験生が大学で学びたいと希望すれば、大学は可能な限り、受験生の希望のかなう体制を整えるよう工夫するわけです。あるいは、歩行困難な市民のために、公共施設には自由に出入りできるスロープやエレベーターを設置するといったことであり、目の悪い人のために、駅のホームには転落を防止するガードを設けるといったことです。点字ブロックなどもその一環ですが、本学のキャンパスにも敷いてありますね。
この「障害者差別解消法」に関しては、施設などの充実改善を始め、本学でも早くから実行に取り組んでおります。皆さんも、街の中や駅などの公共施設でこうした工夫や試みは、ごく普通に目にしていることと思います。障害のある人々とわれわれの間にある、社会的障害物をどう工夫して取り除くか、つまりどのような合理的配慮によって隔たりを乗り越えるかというのが、この法律の趣旨だといえるようです。
さて、この法律が制定されるまでに、障害者への差別を解消しようとする試みは各地でなされて来て、地方行政レベルでも多くの成果を挙げています。私の友人に、千葉県で差別解消条例の試みに取り組んだ、野沢和弘という新聞記者がいます。今は大学の教員になっていますが、十数年前、差別解消条例の試みに彼は千葉に住む健常者、障害者とともに取り組みました。その活動の印象的なエピソードとして、直接、野沢さんから聞いた話ですが、正確を期するために、ここは彼の講演記録(「条例のある街~千葉県からの報告」2011年6月4日 於、大分)から「視覚障害者Tさんのジョーク」という見出しの部分を参考にして話してみましょう。
条例制定の活動に参加していた、全盲のTさんという朗らかで、話し好きな中年男性が、活動仲間の健常者たちに、こういう興味深い話をしました。「障害とは何なのか、根本的に考えてみましょう。障害者はどの町でも同じくらいの割合で生まれています。神様はそうしています。ところが神様がイタズラをしてこの町で私のような眼の見えない人が多く生まれてきたら、この町はどうなりますかね。私が市長選挙に立候補すると、多分当選するでしょう。
市長になった私は福祉予算を倍増するには別の予算を削るしかない。いろいろ研究した結果、この町でゼロにできる予算を発見した。それはこの町の市役所とか公民館、警察とか公共施設にある明り、電灯をすべて失くしてしまう。我々、目の見えない人間にとって灯りというのは無駄なもので、何億円もの電気代を削り地球温暖化防止にも貢献できるはずであり、一般市民の家にも普及させたいと「灯り禁止条例」をつくる。そうしたら少数派の一般市民は怒って飛んで来るはずで、「市長、何を考えているのだ。我々は家に帰ってろうそくで生活をしろというのか、ふざけるな!」と当然、抗議するわけです。
しかし、その抗議もTさんには織り込み済みで、どういう答えをするかといったら、「皆さんの気持ちはわからないでもありませんが、一部の人のわがままには付き合いきれません。少しは一般市民(多数派を占める目の見えない人)のことも考えてみてはどうですか?」と答えてみたいと話したそうです。
もちろん冗談まじりの話ですが、私はドキッとすると同時に、私の気づかなかった問題、正確にはあまり意識して来なかった問題がはっきりと見えるように思いました。健常と障害という「違い」は同時に多数派と少数派の「違い」でもあります。私たちがともに生きようとするさまざまな「違い」にも、多数派と少数派の問題が重なっている場合があります。
この場合、多数派が気づかないのは、少数派に対する自分たちの細やかな理解の不足、欠如だと思います。多数派の常識や利害にとらわれて、そういう理解不足や欠如をが生まれるのでしょう。千葉県のTさんの冗談まじりの話は、そこを逆説的に衝いたわけです。目の見えない者の常識や利害を押し通そうとすれば、目の見える者たちは大いなる不都合を被る場合もあるだろう、とTさんはいっていたのです。
私たちは、社会のいろいろな場面で障害を持つ人に多数派の流儀を押し付けているはずです。あたながたは少数に過ぎないのだから、身の程をわきまえてほしい、と暗黙に言っていることがたくさんあるように思います。これはもちろん、健常者と障害者との間にある「違い」にとどまる話ではありません。多数派と少数派の「違い」のほかにも、強い者と弱い者との間に「違い」がある場合も、似たような問題が起きているのでしょう。いま世界に起きているさまざまな戦い、紛争、差別問題も「違い」の上にさらに多数と少数、強者と弱者の関係が重なっているケースが多いといえます。
こういう問題には明白な結論や決定的な解決策などはあるはずもないのですが、その有効な方法として、「障害者差別解消法」の基本的な考え方、「合理的配慮」などが参考になるかと私は思います。「違い」のある者同士の間に立ちはだかるさまざまな壁を、合理的に取り払っていくような知性の在り方です。少数派や弱い立場の抱える「違い」に対しては、思いやりとか同情といった情緒的な手段ではなく、その隔たりを知的に理解し、知的に埋めて行こうと考えてみる冷静な姿勢がきわめて有効なのだろうと私は信じています。
皆さんが4年間、学んだ本学、愛知淑徳大学は「違いをともに生きる」という理念を掲げて来ましたし、これからも高く掲げて行きます。「違いをともに生きる」とは、あらゆる他者との違いをわきまえ、その存在をフェアに認め、深く理解し合っていくということでしたね。どうか、「違いをともに生きる」という考え方を、心の底にずっと温めつづけ行ってほしい。特に、皆さんと比べて明らかに少数の立場にある人、あるいは皆さんより弱い立場にある人の抱えている「違い」に対しては、敏感で知的なアンテナを育てて行ってほしいと願います。皆さん自身をも含めて、多くの人が居心地の良い社会、さらには世界を実現していく道はその努力から開けていくものと私は信じたいと思います。
最後に、皆さんが、より良い人生を築き上げていくことを願って、私の「贈る言葉」といたします。
令和7年3月18日
学長 島田 修三