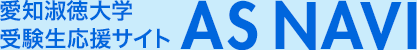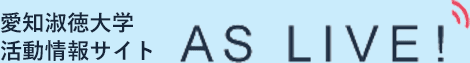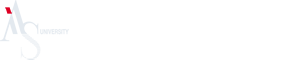医療貢献学科 言語聴覚学専攻
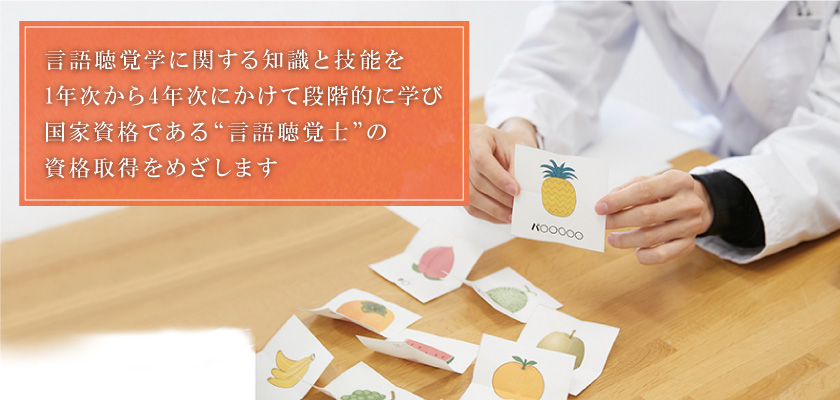
言語聴覚学専攻では、ことばや聴こえに障がいのある方を支援する言語聴覚士の資格取得を目標とし、コミュニケーション障害学、医学、心理学、言語学などを学び、専門性と科学的思考力を身につけます。人の痛みに共感し、共に歩めるやさしさや、障がいのある方と社会の間に立ち、障がいへの理解を深め、環境を改善していく強い心、その両面を兼ね備えたコミュニケーション障害学のスペシャリストを育成します。
身につく力
- 言語聴覚士として、ことばや聴こえに障がいのある方を支援するために必要な知識と技能
- 病気や障がいのある方、高齢者に寄り添い、問題を解決するための意欲・判断力・コミュニケーションスキル
- 科学的な根拠に基づいて実証的に分析し、論理的に思考する能力
言語聴覚学専攻の特色
「言語聴覚士」の
国家試験受験資格が取得可能ことばや聴こえの障がいを的確に判断し、訓練計画を立て、言語的コミュニケーション能力の改善を図る言語聴覚士の国家試験受験資格が卒業と同時に得られます。
言語聴覚士、医師、
音響・言語学者らによる専門教育言語聴覚士、医師の他、音響学、言語学や心理学などの専門家も講義を担当。生きた知識や技能を修得できます。新しい評価方法、訓練方法の開発にも挑める人材を育成します。
全国約52施設の実習先で
高い臨床能力と人間性を養う愛知淑徳大学クリニックの他、全国各地の医療機関とネットワークを結んでいます。現場で役立つ知識や技術修得のため、医療機関などでの体験、見学、実習を実施しています。
言語聴覚学専攻の魅力
体験・経験から理解につながる学び
体験学習を多数取り入れ、実践力と科学的思考力を身につけます。
実習
実習レポート学外実習を経験して詳しく読む
-

-
患者さんとの関わり方や、チーム医療の大切さを実感しました。
大島 巧巳さん
健康医療科学部 医療貢献学科 言語聴覚学専攻 (愛知県立横須賀高等学校 出身)2024年度卒業
実習先
日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院
3年次後期に、耳鼻咽喉科で聴覚領域での実習をおこない、各種聴覚検査や補聴器装用について学ぶことができました。初めの4週間は見学が中心、後半の4週間は患者さんに検査を実施し、検査結果を説明するまでの一連の流れを経験しました。8週間の実習でしたが、言語聴覚士の方々が患者さんとどのように関わっているか、特にコミュニケーションの取り方に注目しました。言語聴覚士や医師、看護師などが互いを尊重し、患者さんに対して最善を尽くすチーム医療も目の当たりにし、自分の仕事に誇りを持ち、周りに信頼される言語聴覚士になりたいという思いがさらに強まりました。
-

-
実際に検査や訓練をおこない、言語聴覚士の重要性を再認識。
小林 美夕紀さん
健康医療科学部 医療貢献学科 言語聴覚学専攻 (富山県立南砺福野高等学校 出身)2023年度卒業
実習先
慶應義塾大学病院
3年次前期の学外実習では、小児領域の構音検査や聴覚検査、構音訓練に携わりました。検査を受けるお子さんの目線に立って、わかりやすい話し方や楽しめる訓練を工夫。自作のすごろくやなぞなぞを使った発語の訓練に、笑顔で取り組んでくれたことが喜びとして心に残っています。また、お子さんやご家族に検査結果を説明する際、自分が伝える一言一言が訓練や治療に向かう気持ちに影響することを実感。チーム医療の一端を担う言語聴覚士としての専門性やコミュニケーション能力を身につけたいと、今後の学修や実習への思いが強くなりました。
-

-
患者さんに必要なことを瞬時に見つける、現場ならではの体験
内木 麻莉子さん
健康医療科学部 医療貢献学科 言語聴覚学専攻 4年生(岐阜県立大垣北高等学校 出身)2020年度
実習先
岐阜県総合医療センター
検査や訓練の見学や実施の他、脳梗塞などの手術直後や意識障がいのある患者さんの症例も見学させていただきました。どんな検査が適切か、今すべきケアは何か、慢性期ケアにどうつなぐかなど、急性期病院ならではの実習ができました。訓練では、一人あたりの訓練時間が限られる中、短時間で患者さんにとって優先すべき訓練内容を導き出す大切さを経験。そのためには病室での様子を知ったり、訓練時間以外でも積極的に話しかけたりと、患者さんに常に寄り添う姿勢を持つことも必要だと学びました。
-

-
患者さんと接する言語聴覚士の姿から、コミュニケーションの鍵を見つけた。
池田 奈緒花さん
健康医療科学部 医療貢献学科 言語聴覚学専攻 3年生(2019年度)
評価実習では、病院で小児領域を担当。主な実習内容は、言語聴覚士の方が検査をするところを見学させていただいたり、カルテを見て患者さんの情報を書きだしたりすることでした。時には、私が検査を担当させていただくことも。学内実習で障がいを持った患者さんと関わった経験はあったのですが、いざ重度の麻痺を持っていたり肢体不自由だったりする患者さんを目の前にすると、「何かあったら大変」と不安になり、関わり方が消極的になってしまいました。このままではだめだと思った私は、言語聴覚士の方の行動を観察し、患者さんが安心できる喋り方や目線などを見て学び、少しずつヒントを見つけていきました。そうして習得した知識や技術を、自分が担当する検査で実践。患者さんとも自然に関われるようになり、実習が終わるころには自信を持って検査できるようになりました。
また、病院には特別支援学校が隣接しており、患者さんが学校でどんな行動をして、どんな問題を抱えているのかを学校教諭や言語聴覚士、作業療法士などの間で共有する「多職種連携」に取り組んでいました。今後の医療現場において多職種連携は非常に重要な課題となるため、学生のうちにその現場に関われることは、貴重な経験だったと思います。
今後の実習では、これまでの実習内容に加えて、評価の結果から患者さんが抱える課題を探したり、自分で訓練を考えたりします。また、成人領域を担当するため、検査内容や環境も大きく変わります。評価実習で学んだ患者様との接し方を忘れずに、成人の患者さんに合わせた話題を予習して総合実習に臨みたいです。
実習報告会
1回の学外実習では、1カ月から2カ月の長期にわたり実際の医療現場で患者さんに接し、実際に検査や言語訓練を経験します。実習後には学外実習で経験した症例や検査、訓練などを発表する機会を設けています。実習後の学生にとっては自身の実習を振り返り理解を深める場に、実習前の学生にとっては自身の実習をイメージする場として、貴重な時間となっています。
施設・設備詳しく読む
小児集団言語訓練室
子どもの言語訓練の実習をおこなうための訓練室です。感覚統合を促すさまざまな遊具を設置し、子どもの行動を専門的視点から観察する力を養います。

聴覚検査室
防音ブースが設置された実習室で、現場で実際に使用されているさまざまな検査機器を用いて実習をおこないます。

発声・発語分析室
音声を音響信号として捉え、グラフ化する機器を設置。「音響学」の授業などで使用します。国家試験の科目でもある音響について具体的に学べる場です。

先輩から聞く学科(専攻)のこと在学生・卒業生の先輩が、学びのことを教えてくれます。詳しく読む
-

-
卒業生
畑 ひかりさん
健康医療科学部 医療貢献学科 言語聴覚学専攻
(国立愛知教育大学附属高等学校 出身)2021年度卒業
勤務先:日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院Q 大学ではどんなことを学びましたか?
1年次から、成人・小児・聴覚の分野を幅広く学び、言語聴覚士が関わる領域の全体像をつかみながら、言語聴覚士として必要な知識や技術、コミュニケーションの取り方などを学ぶことができました。現在は聴覚の分野で働いていますが、年齢の低い患者さんの検査をおこなう際には小児の分野で学んだことが活きています。また、学内には実際に医療現場で使用されている検査機器が揃っているため、学生同士で練習し合うことができたり、来校いただいた症例協力ボランティアの方に対して実際に検査や訓練をおこなったりと、検査方法や検査機器に直接ふれながら慣れていくことができました。さらに学外実習では、異なる複数の施設で言語聴覚士の方が働く姿を見学するだけでなく、患者さんのリハビリテーションや聴覚検査など、机上の勉強では得られない経験を積むことができました。
Q 仕事のやりがいを感じるときは?
現在は、耳鼻咽喉科での聴力検査やリハビリのほかに、週4日の補聴器外来にて患者さんの補聴器の調整や検査、カウンセリングをおこなっています。補聴器は装用状態の確認や検査結果をもとに、1~2週間に一度、数カ月かけてその方に適した細やかな調整をしていくことが必要です。同じ聴力でも人によって調整のゴールは異なるため、医師・言語聴覚士・認定補聴器技能者で医療連携をしながら調整をおこないます。調整を何度か繰り返す中で、「聞こえるようになって嬉しい」「耳鳴りが気にならなくなった」といった言葉をいただくと、やりがいを感じます。言語聴覚士がおこなう検査の結果が、補聴器の調整や治療の方針につながるため、今後も素早く正確な検査をおこなえるよう検査技術をより向上させていきたいです。
-
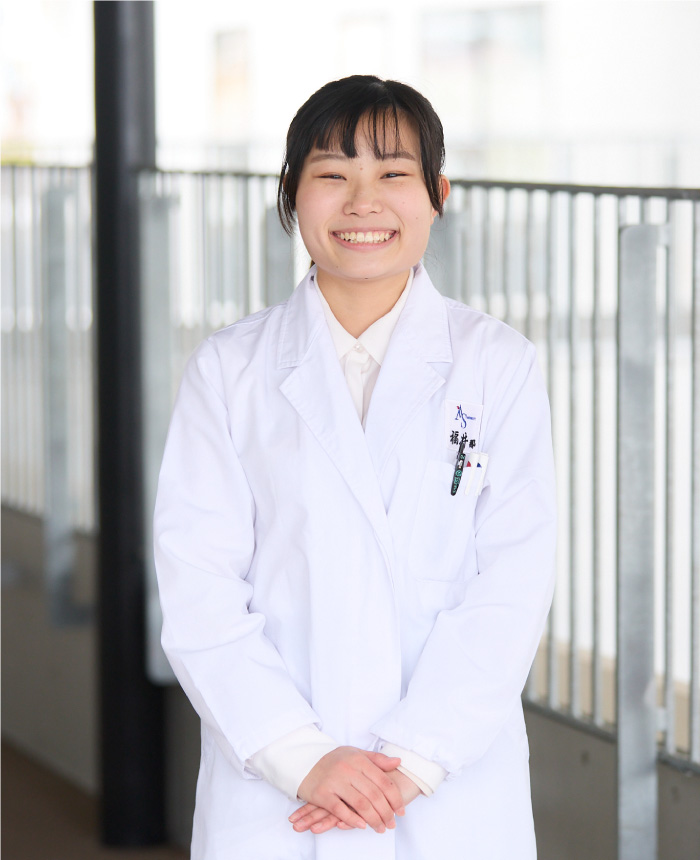
-
在学生
福井 那月さん
健康医療科学部 医療貢献学科 言語聴覚学専攻 4年
(愛知県立津島東高等学校 出身)2023年度
Q この学科(専攻)の魅力は?
言語聴覚士や医師など、医療現場での経験が豊富な先生が多く、臨床現場でのさまざまな事例をもとにリハビリ計画を立てるなどの、実践につながる授業もあります。学生同士で話し合いをしたり、患者さまに合った訓練方法を考えたりする中で、連携することの大切さに気づき、コミュニケーション能力の向上にもつながっています。
Q 印象に残っている学びや授業内容は?
『臨床演習(基礎)』でリハビリテーション計画を立てる実習をおこなったのが印象的でした。本学へ実際の患者さまにお越しいただき、リハビリテーション計画を立てるためのヒアリングをおこないました。患者さまと接することで、授業で学んだ疾患による症状が患者さまの日常生活にどのような影響を与えているか、日常生活で感じている悩みや不安などが明確になり、計画立案に大きく影響しました。適切なリハビリテーション計画を立てるためには、患者さま一人ひとりの不安に寄り添い、生活環境にも配慮しながら、症状に応じた継続しやすい立案をすることが必要だと気づくことができました。
Q 今後、学科で身につけたいことは?
言語聴覚士は、医師や看護師などさまざまな職種の方々と連携し、患者さまのリハビリをおこないます。グループワークを通して意見を出し合い、考える力やコミュニケーション能力を活かしながら、患者さまをはじめ、さまざまな職種の方からも頼りにされる言語聴覚士になれるよう、技術力やコミュニケーション能力をさらに磨いていきたいです。
4年間の学び(2025年度)
 |
|---|

|

|

|
|---|---|

|

|
PICKUP!科目詳しく読む
言語発達学
言語発達を各発達段階における知能、認知、社会性、情緒、運動の各能力との関係において捉え、各発達段階における言語発達の内容を、音韻、構文、意味、語用などの言語学的視点から理解します。
聴覚障害Ⅰ
小児や成人の聴覚障害について、障害の原因と種類・特性、病態、聴力の程度に合わせた補聴方法などを学修。また検査法やコミュニケーションの評価、連携についての知識を修得します。
高次脳機能障害Ⅰ
大脳の構造・機能をふまえた上で、脳損傷による言語以外の行為、認知、注意、記憶、遂行機能などの高次脳機能障害に関する症状とその発現メカニズム、評価について基礎的な知識を学修します。
基礎的臨床技能演習
言語聴覚士の仕事を実践する学外実習Ⅱ・Ⅲに向けて、成人領域、小児領域、聴覚領域で用いられる代表的な評価法、検査法の基本的知識や考え方・手技を、演習および臨床技能評価を通して学修します。
資格・免許
取得できる資格・免許
- 言語聴覚士(国家試験受験資格)
言語聴覚士国家試験合格率
2024年度 80.5%(合格者33名/受験者41名)
就職
主な就職実績
【東北】
- 社会福祉法人グリーンローズ オリブ園
【関東・甲信】
- 順天堂大学医学部附属順天堂医院
- 一般財団法人多摩緑成会 緑成会整育園
- 社会医療法人社団東京巨樹の会 東京品川病院
- 医療法人社団城東桐和会 タムス市川リハビリテーション病院
- 放課後等デイサービス あんSchool ホップ
- 医療法人徳洲会 湘南藤沢徳洲会病院
- 信州大学医学部附属病院
【東海・北陸】
- 医療法人秋田病院
- 公益社団法人日本海員掖済会 名古屋掖済会病院
- 社会医療法人杏嶺会 こども発達センターあおむし
- 医療法人香徳会 メイトウホスピタル
- 医療法人啓仁会 豊川さくら病院
- 医療法人珪山会 鵜飼リハビリテーション病院
- 社会医療法人杏嶺会 一宮西病院
- 医療法人桂名会 重工大須病院
- 愛知医科大学病院
- 医療法人凰林会 榊原白鳳病院
- 豊橋市民病院
- 医療法人緑葉会 関谷耳鼻咽喉科
- 愛知県厚生農業協同組合連合会 安城更生病院
- 医療法人愛生館 小林記念病院
- 国立研究開発法人国立長寿医療研究センター
- 医療法人良実会 ハピネス歯科おとなこども歯科
- 藤田医科大学病院
- 医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院
- 医療法人偕行会 名古屋共立病院
- 社会医療法人明陽会 第二成田記念病院
- 社会福祉法人名古屋市総合リハビリテーション事業団
- 名古屋市立大学病院
- 医療法人東樹会 あずまリハビリテーション病院
- 医療法人白山会 白山リハビリテーション病院
- 大垣市民病院
- 社会医療法人厚生会 中部国際医療センター
- 社会福祉法人土岐市社会福祉協議会 土岐市幼児療育センター
- 三重大学医学部附属病院
- 市立四日市病院
- 三重県立聾学校
- 社会福祉法人聖隷福祉事業団
- 地方独立行政法人静岡市立静岡病院
- 金沢大学附属病院
- 医療法人光ヶ丘病院
【近畿】
- 関西医科大学附属病院
- 公益社団法人京都保健会 京都協立病院
- 京都府立 聾学校
- 社会福祉法人愛徳福祉会
【中国・四国・九州・沖縄】
- 医療法人徳寿会 鴨島病院
- 社会福祉法人輝翔福祉会 他
ゼミナール(2025年度)
| 籠宮 隆之 | ゼミ | 話し言葉の科学 |
| 志村 栄二 | ゼミ | 話し言葉や飲み込みの障がい |
| 竹中 啓介 | ゼミ | 失語症やその他の高次脳機能障がいのある方に対する評価、支援 |
| 長嶋 比奈美 | ゼミ | 言語聴覚障がい児/者のコミュニケーションについて |
| 船﨑 康広 | ゼミ | 認知・言語・コミュニケーションの発達に問題を持つ方々の指導、評価、支援 |
学生たちの研究テーマ例
- 絵本の読み聞かせにおける自閉スペクトラム症児の反応・行動の変化
- 音声認識アプリ(UDトーク)を活用した聴覚障害学生への情報保障支援方法の検討
- 重度口腔乾燥を合併したパーキンソン病のある人に対する香り刺激と唾液腺マッサージの試み
- 失語症の聴取評価におけるST学生と他学生間との差
- 語音聴取評価検査「CI-2004(試案)」を用いた各スピーカ法の比較
- 音声認識ソフトウェアによる発話明瞭度評価の検討